浮舟
2021/10/27
 銕仙会能楽研修所(南青山)で青山能。仕舞二番と共に能「浮舟」です。
銕仙会能楽研修所(南青山)で青山能。仕舞二番と共に能「浮舟」です。
仕舞「三輪」(長山桂三師)はクセ。されどもこの人、夜は来れども昼見えず
から三輪山の神婚伝説を連綿と描き、じわりと心にしみる謡と舞です。ついで「鵺」(浅見慈一師)は東三条の林頭に暫く飛行し
から、退治された鵺の亡霊がうつほ舟で淀川に流される最期の場面。厳しい表情に気迫をこめて特徴的な型の数々(射伏せられ、剣を賜り、流レ足で川面を漂い、招キ扇から飛返リ……)が展開し、地謡の四声ユニゾンが声の壁を作って後押しするよう。

舞台と見所が近い銕仙会のこの親密な空間で観るようになって、遅ればせながら仕舞の面白さがわかってきたような気がします。
浮舟
「桐壺」から律儀に読み始めてなんとか須磨流寓までは行き着くものの「玉鬘」あたりで完全に持て余し、ピンポイントで女三宮降嫁あたりを読んで宇治十帖は手付かず……というのが一般的な『源氏』体験ではないかと思いますが(←自分のことだ)、浮舟はその宇治十帖の中で薫と匂宮の間で揺れ動き、一度は死を決意するものの高僧に救われて仏門に入る女性です。この幸薄き登場人物を主人公とする「浮舟」は『源氏物語』宇治十帖に題材をとった執心女物で、守護大名細川満元の家臣・横越元久が作詞し、節を世阿弥が付けたもので、世阿弥自身が高く評価した曲だそう。前回「浮舟」を観たときは予習が足りずに歯痒い思いをしたので、今回はそれなりに勉強して臨みました。
寂寥たる笛の音に呼ばれて登場した諸国一見の僧(舘田善博師)は長谷寺参詣の後、京へ上る途上。初瀬から宇治への道行の謡は森常好師を思い出させる美声で、メロディアスなその謡は「歌」と書きたくなります。
ワキが脇座に着座したところでヒシギ、脇正面に柴積舟の作リ物が置かれた後、前シテ/里女(馬野正基師)が登場しました。女笠をかぶり面は泣増(是閑作・馬野家蔵)、紅浅葱段替の上に藤やさまざまな花の文様を載せた唐織の右肩を脱いで左手に水棹を持ち一声とともに静かに舞台に進んだシテは舟の中に入ると一セイ。しばらくシテの深い声音に聞き惚れているとワキが声を掛けて、ここから『源氏物語』の浮舟の話が語られます。地謡の初同さなきだに古の、恋しかるべき橘の小島が崎を見渡せば
以下を謡う間、棹を構え、あるいは笠に手をやって遠く見やる姿からもそこに宇治川の情景が見えてくるよう。やがて笠を置いて舟から下りたシテは正中に下居し、その面に深い思いをこめた表情を湛えながらの居グセとなりますが、そこでは宇治まで忍び訪ねて浮舟を小舟にさらった兵部卿の宮(ここでは匂宮のこと)との逢瀬が有明の月澄み昇る
水の面もくもりなく
汀の氷踏み分けて
など『源氏物語』「浮舟」からの引用を多用して語られます。この間、居グセとは言いつつシテは昔を思い出す風情で月を見上げたり、腰を浮かして水面を眺めたり。しかし薫中将を思い切ることもできない浮舟は、懊悩の末に終に跡なくなりにけり
。
ここでワキがシテに身の上を尋ねたところ、自分は宇治ではなく小野(比叡山麓)に住む者であり、物の怪に憑かれ悩んでいるのであなたの法力を頼みと思いつつ待っていると告げて、常座で小さく回って送リ笛を背に橋掛リを下がっていきました。
通りがかったアイ/里人(野村万之丞師=弛みのない語り口)の言葉によって先ほどの女が浮舟の亡霊だと確信したワキが脇座に座したまま今もその、世を宇治山の道出でて……小野の草叢露分けて、あはれをかけて弔はん
と美しいビブラートで待謡を聴かせた後に、「おや、これは?」と思わせる大小のすこぶる長くしかも緩急を伴った囃子が続きました〔後述〕。やがて笛が入って橋掛リに登場した後シテ/浮舟の姿は、面はそのままに長鬘を左右に垂らし、箔の光沢が美しい裳着胴に緋大口ですが、その姿は横川の僧都に拾われた浮舟の「白き綾の衣一襲、紅の袴ぞ着たる」という『源氏物語』の描写を引き写しているように見えます。
一ノ松から二度目の一セイを儚げに亡き影の絶えぬも同じ涙川。よるべ定めぬ浮舟の、法の力を頼むなり
と謡ったシテは、続くあさましきや、本より我は浮舟の
から声量・音程とも一段高くして激情にとらわれた様子。ここからは生前、身を投げようと夜分に外に出た浮舟が烈風と荒波の音の中で知らぬ男
(悪霊)にかどわかされるさまが今度は『源氏物語』「手習」を引用しつつシテによって謡われますが、一ノ松辺りで心定かでない様子で二、三歩後ろずさったシテは、男に誘われるままに浮遊した様子で橋の上で回るとゆらめく笛の音に導かれて舞台に進み、常座で拍子を踏みながら心も空になりはてて
。そしてここからシテは緩急自在の囃子方と共に、常座と角の間を行き来しながら足拍子を鳴り響かせ、あるいは角から舞台上を廻って常座で回る激しい動き(カケリ)を通じて、取り憑かれ心乱れるさまを示しました。
カケリを終えたシテがあふさきるさの事もなく
と強く謡った後に、詞章は次の歌を引用します。
橘の小島の色は変はらじを この浮舟ぞ行方知られぬ
これは浮舟を連れ出して宇治川を渡る匂宮の贈歌年経とも変はらむものか橘の 小島の崎に契る心は
に対する浮舟の返歌で、「水に浮く小舟のような私の身はどこへ漂っていくかもしれません」というこの下の句は『源氏物語』の第五十一帖が「浮舟」と呼ばれる所以ともなっている箇所ですが、此浮舟ぞよるべ知られぬ
と改められたこの部分の詞章を指して世阿弥は「この所、肝要なり」とし、一日も二日もかけるほど念入りに謡い込むようにと『申楽談儀』の中に記しているそうです。そして馬野正基師の強く味わい深い節を伴う謡もまた、なんとも言えず聞くものの胸に染み通ってくるような感覚を覚えるものでした。
生前、横川の僧都の祈りによって物の怪から逃れたものの、死後もなお惑い続けていたシテは、初瀬観音の慈悲と僧の弔いにより執心を晴らすことができたことを感謝してワキに合掌すると、橋掛リに下がって一ノ松からワキを振り返った後に幕の内へと消えていき、最後にワキが正面を向いて立ち尽くした姿で杉の嵐もや残るらん
と曲を終えました。
終曲後に長山桂三師ひとりが舞台に戻ってきての事後講座では、この曲は初めて能を観る人にはハードルが高かったかもしれないという前置きを置いて、親しみやすい語り口での曲解説が行われました。
その中で、この曲は世阿弥にとって自信作であると共に故・観世寿夫師も好み、銕仙会において大切に扱われてきた曲であると語られ、ついで演出上の工夫としてこの日の装束や作リ物、面の選択、後場で橋掛リから舞台に入るときの運びの特徴が説明されましたが、待謡から後シテが出てくるまでの間の長い囃子についても解説されました。それによるとここでは「半流はんながし」という特殊な手が打たれており、共に大倉流の大鼓・小鼓による「半流」は史上初であったため、大倉源次郎師が手組を整理してこの日の演者(大倉慶乃助師・田邊恭資師)に伝授したものだそうです。
実は、この日の大鼓は終始打音が強くて耳に痛く、ちょっとつらくなるほどだったのですが、なるほどそれで気合いが入っていたためかと妙な納得をしてしまいました。ともあれ、その緩急は宇治川の流れを示しているようでもあり浮舟の流されゆく姿を示しているようでもあり、観る者がイメージを膨らませてほしいところであるというのが長山桂三師の説明でした。
予習の甲斐あって『源氏物語』での浮舟の運命を思い、さらに謡曲「浮舟」の見どころ仕どころも見逃さずに鑑賞することができましたが、後場のカケリで示される憑き物の意味ばかりは今ひとつわかりませんでした。中入前にシテがワキになほ物の気の身に添ひて、悩む事なんある身なり
と言っていますから『源氏物語』の中で入水を企てた浮舟に取り憑いた僧の悪霊がこの曲では死後の浮舟にも引き続き祟っているのだろうと一応は理解できますが、一度は救われたはずの浮舟が救済を求め続けなければならない理由は、薫によって宇治に囲われていながら情熱的な匂宮に迫られてよるべ
なく漂い、落飾後ですらも小君の来訪に乱れを隠せなかった(「夢浮橋」)生前の弱い心のせいだとすれば足りてしまいそう。そうなっていればこの曲はしっとりとした鬘物として扱われていたかもしれませんが、原典で登場する物の怪を無視するわけにもいかずオカルトな憑き物の能にされたのなら、この曲(の主人公)が気の毒のようにも思います。
もっとも、こうした見方はたぶん理解が浅く、何か読み落としていることがあるのだろうと思いますが、その解明は次にこの曲を観るときまでお預けです。
配役
| 仕舞観世流 | 三輪クセ | : | 長山桂三 | |
| 鵺 | : | 浅見慈一 | ||
| 能観世流 | 浮舟 彩色 |
前シテ/里女 | : | 馬野正基 |
| 後シテ/浮舟 | ||||
| ワキ/旅僧 | : | 舘田善博 | ||
| アイ/里人 | : | 野村万之丞 | ||
| 笛 | : | 藤田貴寛 | ||
| 小鼓 | : | 田邊恭資 | ||
| 大鼓 | : | 大倉慶乃助 | ||
| 主後見 | : | 鵜澤久 | ||
| 地頭 | : | 西村高夫 | ||
あらすじ
浮舟
→〔こちら〕
この日、見所に置かれていたチラシ類の数々の中に、12月11日に横浜能楽堂で上演される「紅葉狩」のチラシも含まれていましたが、その惹句がこれ。
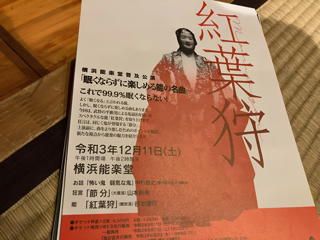
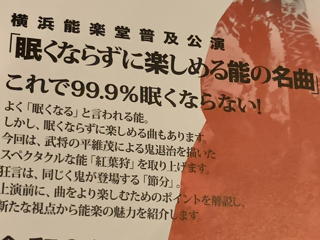
「これで99.9%眠くならない!」って、この曲は眠眠打破なのか?しかしそれでも「100%」と言い切れないあたりに能楽師の誠実さというか謙虚さというか自信のなさというかを感じて、思わず微苦笑してしまいました。