巣鴨塚 ハルの便り
2025/12/23
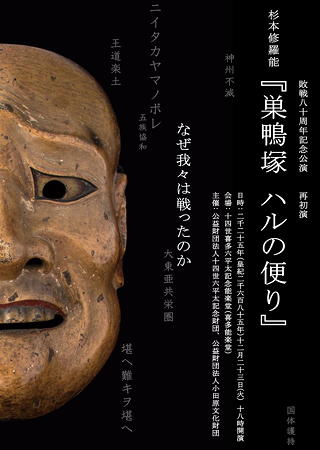 今年最後の観能は、喜多能楽堂(目黒)で杉本修羅能「巣鴨塚 ハルの便り」。
今年最後の観能は、喜多能楽堂(目黒)で杉本修羅能「巣鴨塚 ハルの便り」。
本作は、写真家・現代美術作家として知られる杉本博司氏が入手したという板垣征四郎(日本陸軍大将・第二次世界大戦終結後にA級戦犯として巣鴨拘置所にて処刑。以下敬称略)の漢詩を舞台形式で公表することを企図して杉本氏によって書かれた「能 巣鴨塚(修羅能)[1]」を原作とし、以下の能楽師の手によって能の形式に改められた新作能です。
- 能本:川口晃平
- 〔演出〕大島輝久 / 野村萬斎
- 作調:亀井広忠
上記の経緯からわかる通り、タイトルの「巣鴨塚」は巣鴨拘置所を、「ハルの便り」は日米開戦を決定づけたハル・ノートをそれぞれ指しています。そしてこの能は、今年8月15日にやはり喜多能楽堂で初演されており、今回は「再初演」と銘打たれての上演です。
 |
 |
見所に入ってみると、初演時の写真[2]でも見た「巣鴨塚」の標柱が舞台上(大小前)に立てられており、舞台の前縁には唐織二着・厚板一着が掛けられていました。ただ、初演時にはあの標柱は正先に置かれていたはずですし、配布されたプログラムに掲載されている詞章を見ると上演日が今日であることを念頭においた記述(歳末の市
師走の二十三日
)もあることからして、8月15日の初演時とは詞章や演出が異なるであろうことが窺えました。

上演前にまず杉本氏が立って、穏やかな語り口でひとしきりの解説を行いました。その内容(順不同)をかいつまんで記すと次のとおりです。
- 米国在住の自分は、かつて日本が負けるとわかっている戦争をした理由を問われることが多く、その問いに対する答を能というかたちで表現しようと思っていた。能に多くの題材を提供する『平家物語』が、源平の時代から時を経て当事者がいなくなった頃に琵琶法師による語り物として成立したように、先の大戦の話も敗戦から80年になるいま書き残しておかなければならないと考えた。右とか左とかを離れて、太平洋戦争とはどういうものだったかを俯瞰して語り継ぎたい。
- 10数年前に戦争画展覧会を企画する中で市ヶ谷を訪ねたとき、板垣征四郎の揮毫帳のコピーを入手した。この揮毫帳は東京裁判の日本側弁護団への御礼として巣鴨拘置所の獄中で回されたもので、板垣の揮毫は「感無量」、廣田弘毅は「飛龍在天」、東條英機は「一誠排萬難」。これらの後に板垣が「自序」と題して自分の生涯を振り返る漢詩を書いており、その内容は自己弁護ではあるが、板垣の教養の高さを示す見事なものだった。これを読んで、能の謡本にできるのではないかと考えた。
- そこでまず原案を13年前に『新潮』誌上で発表し、10年前に池袋のあうるすぽっとで朗読劇として上演した。その後、コロナ禍をはさんで観世流の川口晃平師の手を借りて謡曲化し、ようやく今年の上演に漕ぎつけた。初演は8月15日だったが、板垣征四郎が処刑された12月23日こそその御霊を呼び寄せるにふさわしいと思い「再初演」することにした。なにぶん新作能なので、客電を暗くせず、配布したパンフレットに掲載した謡本(無料です)を読みながら観られるようにしている。
このような説明をした杉本博司氏が着席すると、舞台上の塚と装束はそのまま(!)にお調べが始まり、やがて囃子方と地謡が舞台上に登場しました。「配役」を見ればわかるように、この日の舞台のシテ方はシテ・ツレの一人・後見が喜多流でツレの一人・地謡が観世流というハイブリッドになっています。
巣鴨塚 ハルの便り
狂言口開。登場したアイ/この辺りの者(野村萬斎師)の出立を見ると明るい色の羽織の下に見えている襟元がなぜかワイシャツのカラーで、その名乗リも詞章では巣鴨辺りに住まいする者
となっているのに萬斎師曰く「杉の本の博司と申す者でござる」。白いシャツが好きだと自分の出立を説明し、「写真・建築などいろいろやっているが、古美術を収集してその滋養により作品の質を上げるのが何よりだ」と語って見所の笑いをとっているうちに、歳末の市が開かれている場所に到着します。正先に並べられていた装束はこの市に出された商品だったというわけで、それが満洲国の品であることを知ったアイが昔に思いを馳せていると笛や太鼓が賑やかに奏され始め、ここから「五族協和の舞」が始まります。
まず舞台に現れたツレ/舞人・男(鵜澤久師。直前までてっきり光さんだと思っていました)の出立は、プログラムに掲載されていたリストの通りだとすれば杉本博司氏所蔵の狩衣を着用し、浅葱色の大口を穿いて面は慈童。この舞人・男がひとしきり舞った後でもう一人のツレ/舞人・女(大島衣恵師)が登場しましたが、こちらは厚板壺折に朱大口、髷を結い面は小面。手にしているのは男が唐団扇、女が中啓なので、「五族協和の舞」にふさわしくかたや中華、かたや日本です。この二人に誘われてアイも正先の厚板を着用し、三人で舞った後に正先から階に足を下ろして「五族協和!」とユウケン。いつにも増しての怪演を見せた萬斎師は、舞人二人と共に楽しげに橋掛リを下がっていきました。
三人が退場したところで間髪入れずにヒシギが吹かれ、次第の囃子の内に後見の手により舞台前方に残されていた装束二着が下げられて、今度は沙門帽子僧出立のワキ/唐土方の僧(御厨誠吾師)が登場しました。次第枯れ野に春は遠からじ、巡り廻るは因果の春
からの名乗リによれば、ワキは倭国関東を見物に来たとインバウンド風ですが、高層ビル群を始めとする殷賑の中に荒地の塚を見つけて不思議に思う様子。この塚の謂れを知る人が通ってくれないものかと独りごちたワキが脇座に着座したところで、大小がひっそりとアシラウうちに登場した前シテ/老人(大島輝久師)は、右手に杖、左手に白菊を持つ尉出立で三ノ松に立ち、深々とあの世から響く声で春近くして春の陽なく、冬名残りて春の香もなし。げに恐しや春の便り。寂滅亡国の響きあり。国破れて山河あり、春の訪れ恐しや
と謡いました。
この恐しや
という語が謡われたまさにそのとき、小さな地震が起きてかすかな地響き。あたかも板垣征四郎の霊が降りてきたようでした。
しかしシテは動じることなく謡いながら歩みを続け、舞台に入って塚の前に下居し合掌しました。そこへワキが語り掛けての問答を経て、シテの語りによる巣鴨塚の謂れは、かつての大戦で破れた日本が松嵩の中将麾下の軍の進駐を受け、裁きによって七人が師走の二十三日に命を取られた、その巣鴨プリズンの跡であるというもの。ここで中央に移動したシテと脇座のワキは共に下居し、地謡がシテの言葉を引き継いで、板垣の大将が満蒙の地に夢見た王道楽土は幻となってしまったことを謡ったところで、老人があまりに詳しいことを不思議に思ったワキがその素性を尋ねると、シテは自らを板垣の亡霊であると明かします。さらに地謡によるシテの言葉は春の便りの無き世かな。あはれ遠き世は、兵火の憂いを忘れたる、楽土の如き栄えなり。されどかつてを忘るれば、修羅の夜ともなるべきなり。その理をも聞け人よ。夢ばし覚ましたもうなよ
と記憶の風化を戒める内容ですが、このかつてを
以下の部分は驚くほどのフォルテシモで謡われ、ことに聞け人よ
は聞け!人よ!
と聞こえました。
シテが常座に杖を捨てて橋掛リを下がっていった後、肩に籠を提げて舞台に戻ってきたアイが「珍しい品が手に入ったので見せびらかそう」とまず取り出したのは、満洲国衛兵がかぶっていたという兜。ぼそぼそと「どちらが前かわからん」とか「電極をつなぐと危なそうだ」とアドリブを利かせてから、次に取り出したのが南満洲鉄道新京[3]駅の看板(本物)です。そして最後に取り出した巻物は貴重品だと言われて買ったようですが、漢詩が読めないので誰か読んでくれないものかと見回してワキを見つけました。
アイの求めに応じ、数珠を手にして巻物を受け取ったワキは、ここから巻物を読む体で板垣征四郎の漢詩を読むことになります。その全文はパンフレット内の詞章に掲載されていますが、五言を一句として百句からなるその内容は、若き日の文武錬成、大陸での転戦の日々、満洲事変と満洲建国、日中戦争と陸相就任、朝鮮軍司令官就任と太平洋戦争勃発、シンガポール赴任と敗戦、そして最後に未だ衰えない志[4]を明らかにして昭和二十二年秋、市谷にて征四郎書す
と締めくくる(内容的にも分量的にも)長大なものです。これを覚えるのは大変だなと思いつつもワキの朗読に合わせてつい詞章の一字一句を目で追ってしまいましたが(笑)、前の方で一句だけアレだったものの朗々と読み上げ通した御厨誠吾師に、心の中で喝采を送りました。巻物を畳んだときに紺紙金泥経のように細かい文字が書かれているのが見えはしたものの、読み上げているときのワキの視線は動いていなかったので、やはりこれは暗誦だっただろうと思います。
ここでワキがアイに先ほど会った老人の話をすると、アイがその正体を推察してワキに弔いを勧めるのは複式夢幻能の定石通りです。塚に巻物を手向け二人揃って合掌し、ワキの待謡の内にアイが月を見上げると、ヒシギから出端の囃子になってワキは脇座へ、アイは切戸口へ。ややあって一ノ松に進み出た後シテは、異形の面(フライヤーやパンフレットの表紙に見られる十寸髪男)を頭巾に包み、紫地に桐文様の狩衣の右肩を脱ぎ半切は緑地。さすらいの身の浮き雲も散りはてて 真如の月を仰ぐうれしさ[5]
と謡い、強い足拍子で軍靴の響き
をこだまさせるシテの軍装姿を地謡はあるか無きかにかげろう姿
と描写して、観ている方は背筋に冷たいものが走ります。
ここからシテとワキとの掛合いがあってクリ・サシ・クセとなり、そこに先ほどの漢詩のエッセンスが巧みに嵌め込まれていきます。ことにクセの詞章は板垣征四郎が心を砕いた満洲国建国のくだりで、上ゲ端されば王道楽土とて
の前の段に出てくる轟然たり柳条溝
では床几に掛けた姿から扇で深々と床を指し、床が抜けるのではないかと思われるほどの強烈な足拍子一発!から一瞬で袖を巻いて立ち上がる切れ味鋭い型が見られました。また、上ゲ端の後の段では悲しむべし盧溝橋
と謡われるうちに後見から矛を手渡され、舞台上でこれを構え・突き・薙ぎ払いつつの勇壮なカケリから橋掛リに出る姿が板垣の転戦を示しましたが、ここで戦況は一変。日本の山河も街も火の海
となり、夜空を覆うのは白金の鳳
(B29)、帝都の闇も赤々と
燃え(東京大空襲)て、広島も長崎もただ一閃に消え去り
(原子爆弾)ます。
一ノ松(シンガポール?)から遠く舞台を眺めやる姿で母国の惨状を見つめていたシテは矛を置き、我らが科か哀しやな
と足拍子を踏みましたが、広島・長崎の後にも凄惨な戦場の描写は続きました。敵軍が上陸して戦車を連ね、火炎を放つというくだりからは沖縄戦の惨禍を思い出しましたが、タイミングとしては沖縄戦は原爆前なので、これは結果的に回避された本土決戦の様相をシテが脳裏に描いている模様。さらに修羅能の常道に従って太刀を抜き、扇を盾になして舞台上で奮戦したものの、衆寡敵せず修羅の戦ひ哀れなり
と太刀を背後に捨ててがっくり安座したシテは、両手を胸の前に寄せて虜囚の身となったことを示します。続いて地謡が我らに不義は無けれども永久(A級)の科を身に受けて万歳を唱えて失せし身なり
と謡いましたが、このとき万歳を唱えて失せし身なり
は最高音(甲グリ)で謡われ、扇を前に置いて安座の姿勢のまま両腕を高く掲げたシテの姿にはこれ以上ない悲哀が漂いました。
シテは懐かしき閻浮の人よ今もなお 東亜のほかに東亜あるべき[6]
と詠じ、地謡がキリの中でとこしえに礎となりて東亜の春を守らん
と謡うと立ち上がって、朝日に向かって合掌。常座で膝をつき、右袖で面を隠す形で塚の内に消えるさまを示します。通常はここで終曲となり、シテをはじめ演者は順次静かに下がっていくのですが、本作ではさらに橋掛リを下がっていくシテの背後から、地謡が冒頭の次第枯れ野に春は遠からじ、巡り廻るは因果の春
を地取の低さで謡って、シテを見送りました。
まず修羅能として本作における「執心」の所在を見ると、自分の目には次の二点が浮かびます。
- 自分が志を持って建国した満洲国という「五族協和」の「王道楽土」が、夢幻に終わったこと。
- 繁栄を謳歌する現代の人々が、そうした歴史とそこで死んでいった同胞のことを忘れていること。
シテはワキの読経によって呼び覚まされますが、真如の月(悟り)を仰ぐうれしさを言葉にはするものの、修羅道の苦しみがあるわけでもなければ成仏を願っているようでもありません。それよりも、自身の軍人としての生涯をあらためてその最期まで振り返ることで、生前の無念を浄化すると共に歴史を現代に語り継ぎ、さらに東亜の春を守る礎となると最後に告げることで自身の死の意義を再定義できたように見えました。この点では、シテの執心は一応の解決を見たように思えます。
ただ、観ていて「これは見所にとって難しいな」と思った点もあります。
- 板垣征四郎の軍歴は、満洲を含む中国に関わる経歴と太平洋戦争期の朝鮮・南洋での経歴とからなっています。そして、ワキやアイの語りが満洲国に強く結びついているのに対し、特に後場のカケリ以降の修羅は太平洋戦争の再現になっているため、板垣=満洲国という目で見ていくと混乱しそうです。
- シテが前場において(過去を忘れてはならないという)
理を聞け
と迫り、後場の最後に東亜の春を守らん
と約束した相手は、日本人ではなく唐土方の僧です。素直に考えれば、これらの台詞は現代の日本の繁栄を謳歌する人々に向けられてしかるべきだと思えるのですが、そうしなかったのはシテの目線をかつてと同じく東亜全体に向けたかったからでしょうか?
また、漢詩はさておき詞章の中のいくつかの言葉には直感的に引っかかりを覚えました。
報怨以徳の心を持って
:アイから板垣の霊を弔うようにと勧められたワキが発する言葉です。「報怨以徳」とは『老子』に出てくる言葉で、その意味は読んで字の如し。日中関係では第二次世界大戦終了時の蒋介石の対日政策がこの言葉と共に紹介されることがあるようですし、したがって唐土方の僧であるワキがこの言葉を使うことも頷けるのですが、日本人が作る芸能作品の中で登場人物である中国人にこの言葉を言わせるのはどうなのか?武士もののふの本懐
:これはクセの冒頭の海征かば水漬く屍、山征かば草むす屍を晒さんも
に続く板垣地謡の言葉です。将としての板垣にとっては自然な言葉ですし、本作でもそういう文脈で使われているのでいいのですが、それにしても一般の兵士にとっては、板垣ほかの命令によって異国に斃れることは本懐でもなんでもないだろうと思ったり……。我らが科か哀しやな
:キリの中での板垣地謡の言葉(次も同じ)ですが、漢詩の中には出てこない述懐なので不思議に思いました。ただ、後で調べてみたところ、板垣は満洲建国後の日中戦争には賛成しておらず、後に日中戦争が太平洋戦争につながった(ハル・ノートは、日本が中国大陸で得た権益を放棄することを要求した)ことを悔やんでいたそうです。我らに不義はなけれども
:東京裁判において板垣は「満洲事変は侵略ではなく、満洲国も傀儡政権ではない」と主張したそうです。おそらくこれは板垣の偽らざる信条だったのだと思いますが、歴史の評価がこの主張を認めているとは言い難いとすれば、演劇作品の中で板垣にこう語らせてよいものかどうか。
さらに視点を変えてこの能の将来を考えてみると、本作の(「再初演」ではなく)再演はあり得るのかという点にも行き着きます。新作能が再演されるためには、そこに時代を超えた普遍的な主題があることが求められると思うのですが、少なくとも今日の上演は、杉本博司氏の強い情熱があってのことのように思えました。では10年後(敗戦90周年)は?20年後(100周年)は?
思いつくままにああだこうだと書きましたが、こうしてまとめようとすると、やはり自分の近現代史に対する視座のあやふやさを痛感します。また、実はいわゆる「新作能」を観たのはこれが初めての経験で、古典作品のようなお仕着せの「見どころ」を把握できてはいない状態での観能の難しさにぶつかってしまったようでもあります。
いや、本当に難しい……。
なお、本作の能本を書いた川口晃平師のブログ[7]には、師が制作にあたって心を砕いた点が詳細に記されています。ことに歴史認識に関わる次の記述は立派な見識であり、上述の「ああだこうだ」を緩和してくれました。
能本を書く上で難しいと思われたのは、シテの板垣征四郎は(中略)石原莞爾とともに主導した満州事変、満州国建国が歴史上、日本の汚点に近い評価を受けていることでした。
(中略)
当時の軍の所行は絶対に賛美できるものではありませんが、彼らとても歴史に身を投じて日本の国益を守るために力を尽くした人物であり、現代からの視点で不当に貶める必要はないと考えました。
(中略)
思想を開陳するような能はどう考えても醜いですし、板垣の口を借りて僕の歴史観を述べるような舞台にはしたくなかったので、かなりフラットに歴史を見た上で、板垣への弔いを通して大東亜戦争に関わった人々の鎮魂になるよう、形としては保守的な複式の修羅能を作ることにしました。
最後に、純粋に「演劇」として見れば、究極のダイナミズムを発揮したシテ・大島輝久師と川口晃平師率いる地謡陣を中心に、舞台上にいたすべての演者を賞賛しないわけにはいきません。個人的には特に、2017年の「和氣乃會」以来密かに(?)ファンを続けている御厨誠吾師の堂々たる謡と語りに感銘を受けました。そして、本作の再演があるにせよないにせよ、あの「地震」はきっと伝説になることでしょう。
この日の舞台には、杉本氏のコレクションが多数使用されていました。プログラムには「使用予定のもの」という注釈つきでそのリストが掲載されていたので、ここに引用(表記方法を一部変更)しておきます。
- 能面
- 前シテ(老人)「三光尉」(伝三光坊 室町時代末期)
- 後シテ(板垣征四郎常信の霊)「十寸髪男」(伝徳若 室町時代)
- ツレ(舞人 男)「慈童」(伝徳若 室町時代末期)
- ツレ(舞人 女)「小面」(井関家重・河内大掾家重 桃山時代~江戸時代初期)
- 能装束
- ツレ(舞人 男「慈童」)
- 白地万字つなぎ菊牡丹唐草模様襦珍袷狩衣(江戸時代中期)
- 蘭花紋腰帯(令和時代)*満洲国の国章をあしらった腰帯
- ツレ(舞人 女「小面」)
- 鬱金地牡丹唐草紋様厚板(江戸時代中期)
- 白地花唐草模様摺箔(江戸時代後期)
- 舞台上(正先)の装束
- 紅黒縹段松竹梅霞紋様唐織(江戸時代中期)
- 紅地鱗牡丹輪違模樣厚板(江戶時代後期)
- 紫薄茶萌黄段桐唐莫まがき菊模様唐織(江戸時代前期)
- 後シテ(板垣征四郎常信の霊)
- 浅黄茶毘沙門竜甲打板波獅格子輪宝雲模様厚板(江戸時代後期)
- 紫地桐模様袷狩衣(江戸時代後期)
- ツレ(舞人 男「慈童」)
- 小道具
- 南満洲鉄道 新京駅扁額
- 伝 満洲国衛兵兜
- 巣鴨塚(揮毫 杉本博司)
- 上 東大寺塔頭寺院 古材(鎌倉時代)
- 下 東大寺転害門 古材(天平時代)
 |
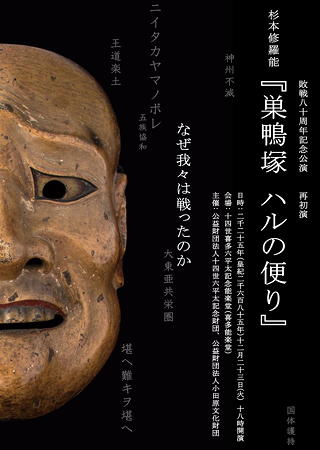 |
配役
| 能 | 巣鴨塚 ハルの便り | 前シテ/老人 | : | 大島輝久 |
| 後シテ/板垣征四郎常信の霊 | ||||
| ワキ/唐土方の僧 | : | 御厨誠吾 | ||
| ツレ/舞人・男 | : | 鵜澤久(初演時は鵜澤光) | ||
| ツレ/舞人・女 | : | 大島衣恵 | ||
| アイ/この辺りの者 | : | 野村萬斎(初演時は野村太一郎) | ||
| 笛 | : | 藤田貴寛(初演時は竹市学) | ||
| 小鼓 | : | 田邊恭資 | ||
| 大鼓 | : | 原岡一之(初演時は亀井広忠) | ||
| 太鼓 | : | 大川典良 | ||
| 主後見 | : | 狩野了一 | ||
| 地頭 | : | 川口晃平 |
あらすじ
巣鴨塚 ハルの便り
中国の僧が東京を訪れ、荒地の中に寂しい塚を見つける。そこへ現れた老人は、それは先の大戦後の裁きにより罪人とされた将兵を処刑した巣鴨拘置所の跡であると由来を語り、自らを板垣征四郎の亡霊であると明かして姿を消す。通りがかったこの辺りの者が、折しも巣鴨で開かれていた歳末の市で買い求めた巻物を読んでくれるよう僧に頼み、僧が読み上げるとそれは板垣の漢詩。この辺りの者の勧めに応じて僧が読経するところへ、武人の装いの板垣の霊が現れ、満洲建国から太平洋戦争を経て自らの処刑に至るまでを回想し、とこしえに礎となって東亜の春を守ると言い残して夜明けと共に塚の内に消えていく。
脚注
- ^『新潮 2013年1月』に掲載。今回の公演に先立って図書館で読むことができましたが、地次第
枯れ野に春は遠からじ、巡り廻るは因果の春
(三句目が定型の七四ではなく七六)から始まり、シテが前・後・後後と三度登場する上に、ラジオ放送が流れたりサラリーマン姿の通訳が現れたり、照明効果や舞台装置(セリなど)の活用が想定されていたりと、オーソドックスな能の形式からはかけ離れたものでした。さらに2015年11月には能仕立ての朗読劇「春の便り 〜能『巣鴨塚』より〜」が上演されていますが、このときは笛・小鼓・大鼓が入り、大島輝久師が舞ったそうです。 - ^「杉本修羅能「巣鴨塚 ハルの便り」」『小田原文化財団』(2025/12/23閲覧)
- ^新京は満洲国の首都。板垣征四郎は、鉄道に乗る際には実際にこの看板を見上げていたはず。
- ^
悠々甘縲独 従容坐陰房 豈無回天期 耿々志未亡 嗤笑任俗世 精誠一迂郎 挙首宇宙窄 唯見至道長
板垣征四郎が処刑されたのは昭和23年12月23日なので、この漢詩が書かれた昭和22年秋から1年以上後のこと。そのためかどうか、この漢詩の末尾八句には死に赴く前の諦観のようなものは感じられない。 - ^板垣征四郎の辞世の歌の一つ。
- ^板垣征四郎の辞世の歌の一つ。ただし本来は
懐かしき唐国人よ今もなほ 東亜のほかに東亜あるべき
。「唐国人」に替えて本作で採られた「閻浮」は、能においては現世という意味(ex.「松風」)。 - ^川口晃平師「新作能「巣鴨塚」解題」(2025/12/23閲覧)