King Crimson
2018/12/18
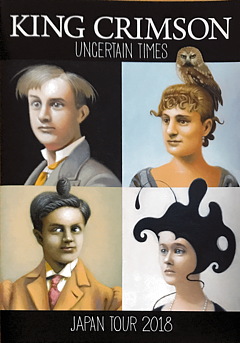 Bunkamuraオーチャードホール(渋谷)でKing Crimsonのライブ。
Bunkamuraオーチャードホール(渋谷)でKing Crimsonのライブ。
このところクラシックに魂を売ったかのような(?)コンサート通いが続いていましたが、自分にとっての王道はやはり、1970年代から親しみ続けてきたこのバンドです。John Wettonはすでに亡く、Bill Brufordも演奏活動から引退してしまいましたが、Robert Frippがステージに立てば、それがどのような編成であろうと(今回は前列トリプルドラムに後列がg, g/vo, k, b, saxのオクテット)そこには終わりのない進化を続ける永久機関=King Crimsonが出現します。
今回のKing Crimsonのツアーは、King Crimsonの結成50周年のアニバーサリー。バンドのフォーマットは2015年の来日時と同じくトリプルドラムですが、前回前列センターに座っていたBill Rieflinは後列中央でキーボードに専念し、新たに加わったJeremy StaceyがPat MastelottoとGavin Harrisonの間でドラム兼キーボードという役割を担う編成となっています。これは、2016年9月からの欧州ツアーの前にBill Rieflinがサバティカルをとったために代役としてJeremy Staceyが加わり、その後Bill Rieflinが復帰したときに入れ替わりではなく追加という形をとったことによるものです。その結果、バンドには3人のドラマーと3人のキーボードプレイヤー(Bill Rieflin、Jeremy Stacey、Robert Fripp)を含む8人が存在することになりました。King Crimsonの50年にわたる歴史の中から生み出された数々の曲が、このダブルカルテット編成によってどのような新しい命を吹き込まれることになるかが、今回のライブの聴きどころとなります。
 |
 |
 |
 |
オーチャードホールのロビーではグッズ販売中。今さらTシャツはもういらないのですが、King Crimsonの歴史本にはつい財布の紐が緩みそうになりました。しかし、今は訳あって徹底的な断捨離を実践中の身。ここはぐっと我慢のしどころです。そのままホール内に入って座席を探すと、私の席は前から6列目の左寄りで、目の前にはPat Mastelottoの複雑怪奇なドラムセットが立ちはだかっていました。
やがて場内に女性の声で、録画録音禁止・演奏中の出入り禁止・公演終了後にTony Levinがカメラを出したら携帯電話・スマホでの撮影は可、といった注意がアナウンスされました。そしてRobert Frippの声で同内容の英文アナウンスがあった後にWelcome from King Crimson! Let's have a good time, Yeah!
と異様に能天気な掛け声が流れて、場内が暗くなりました。
すぐに登場してきたメンバーは、前列の3人のドラマーは黒いシャツ。後列の4人はネクタイにチョッキまたはスーツ姿。サウンドスケープの音や何やら会話のような音声が流れる中、各自チューニングを始め、そしてカウントの声を合図に演奏が始まりました。
Banshee Legs Bell Hassle ("Drumsons Vibrate Goodwill")
3人のドラマーのエレドラによるガムラン風のエスニックな曲。これはほんの触り程度で終わり、すぐにPatのドラムが「Indiscipline」のリズムパターンを叩き始めます。
Indiscipline
背後でギターとチャップマン・スティックがリズムをキープする前で、3人のドラマーが即興的な打楽器のフレーズの受け渡しを繰り返します。その受け渡しの間隔が、最初は小節単位であったものが徐々に短くなり、どこまで行くのか?とハラハラしていたら唐突にカオスのパートへ。Mel Collinsのサックスが咆哮します。その後、ボーカルセクションでJakko Jakszykは「語り」ではなく「歌」を歌い、ここにTony Levinもコーラスを付けることで原曲とまったく異なる雰囲気を作り出していました。曲の最後のフレーズI like it!!
は日本語でイイネー!
。
The ConstruKction of Light
SE的な持続音の上にスティックのうねるリズムが乗り、2人のギタリストのクリーントーンが重なって予想外なこの曲。Adrian Belew期であると共にTrey Gunn期の作品であるこのインスト曲を取り上げるとは思っていませんでしたが、フルートが入ったりストリングスが入ったりとアレンジも自在。
Epitaph
2000年にリリースされた「The ConstruKction of Light」からいきなり1969年のデビューアルバムに戻って「Epitaph」。この展開の唐突感には少々違和感を覚えますが、彼らはこの時代の楽曲については原曲に忠実であることを旨としているらしく、メロトロンの音色やドラムのパターンなど再現度の高いものでした(チンドン屋風クラリネットだけはいただけませんが)。最高潮に盛り上げるところではRobert Frippもキーボードを弾いて、ここでトリプルキーボード全開。Jakko Jakszykは歌い上げるタイプのボーカリストなので、こうしたドラマティックな曲は合っているようです。
Neurotica
Jeremy Staceyのフリーなドラミングを皮切りに2人のドラマーと高速スティックが加わったスリリングなリズムとサックスのアヴァンギャルドなソロ。そして中間のボーカルパートでの構築的な楽器群の絡み合いから再びリズム隊の全力疾走へ。ドラム群の半端ではない音数が絡み合い、そしてびしっと全楽器停止。あまりの手際の良さに呆然。
The Letters
Jakko Jakszykが個人的に最も好きだという『Islands』から、叙情的なこの曲。Tony Levinはアップライトベースを弾いています。ボーカルパートの後にフリージャズ風に崩し切ったカオスなインストセクションを置き、これをサックスが収拾して、Jakkoのボーカルのみの絶唱へ。
Radical Action (To Unseat the Hold of Monkey Mind)
ここからの3曲は現体制での曲。Robert Frippのアルペジオからダーティーなリフの上でドラムのインタープレイの応酬がなされた後、サステインの効いたRobertのギター、全楽器ユニゾンの高速フレーズへ。そしていったん音を止めてから再び重厚なリフと共に同種の曲想が展開する、ヌーヴォ・メタル期を彷彿とさせる曲。
Meltdown
切れ目なく続くボーカル曲。というより、6/8拍子系の重いパターンを叩き込む打楽器群がこの曲の主役であり、その凄まじい音圧の合間にボーカルやサックスやギターが顔を出すという趣き。
Radical Action II
そして再びダークなリフがひとしきり繰り返された後、またしても切れ目なく「Level Five」へ。
Level Five
これも『The ConstruKction of Light』と同じヌーヴォメタル期のメンバーによる『The Power to Believe』(2003年)収録のインスト曲。ここまでの4曲連続演奏でトリプルドラムの破壊力をまざまざと見せつけられた聴衆は、この曲が終わった瞬間、ようやくその圧迫から解放されたという安堵感を覚えながら歓声をあげていたように見えました。
Islands
前半最後の曲は、またまたがらっと曲調を変えて『Islands』から叙情的なタイトルチューンです。ドラムレスでのJeremy StaceyのピアノとMel Collinsのアルトフルートが美しく、メロトロンのストリングス音も古き良き1970年代を思い出させます。最後はGavin Harrisonの控えめなドラムとメロトロンの上でサックスソロがひとしきり演奏され、リタルダンドして穏やかに終曲。
ここで前半が終了し、リスペクトの穏やかなスタンディングオベーションを受けてバンドが袖に下がって休憩となりました。隣では、King Crimsonに詳しいらしい男子に向かって、そこまでは詳しくないらしい女子がぼそぼそと感想を述べています。「ねぇ、なんで新曲ばかりなの?」いや、新曲ばかりというわけでもなかったと思うけど。「ギターを誰が弾いているのかと思ったら、あそこ(上手後方)で座って仏像のように弾いてるじゃん」Robert Frippは仏教徒ではないと思います。「あのシンバルさあ、べこべこだけどいいの?」……その他いろいろ面白い感想や質問をしていたのですが、とてもここには書ききれません。
CatalytiKc No. 9 ("Drumsons Emanate Compassion")
ドラムトリオのゆったりしたリズムが倍速になり、さらに倍速になり……そしてブレイク。
Peace: An End
ボーカルの独唱から入り、Jakko Jakszyk自らギターの美しいアルペジオを加えて懐かしいあの頃へ。
Discipline
曲名どおりアルペジオの訓練のような曲。Gavin Harrisonはハイハットでリズムを刻み、Pat Mastelottoはタムでジャングルビート、Jeremy Staceyは原曲どおりオクタバンを入れていますが、Mel Collinsは原曲にはないバリトンサックスの低音フレーズを加えていました。こうしてみると、ドラムの3人以外ではMelが最も演奏の自由度を楽しんでいるようです。そして2人のギタリストのアイコンタクトで訓練が終わり曲がブレイクすると、Robert FrippとJakko Jakszykはにやり。
Cirkus
この日のセットリストでは『Lizard』から唯一採用された曲。メロトロンやサックスが原曲の雰囲気を見事に再現し、中間部でのTony Levinのベースによるオブリガートも美しいものでしたが、Gordon Haskellの味わい深いボーカルが自分は好きなので、この曲に関してはまあこんなものかなというところ。
Larks' Tongues in Aspic, Part 2
悲鳴を上げるヴァイオリンのSEが流れておっ?と思ったらあの切り裂くようなギターのリフが入ってきて、客席から大歓声。それまで腕組みして聴いているようだった聴衆の身体のノリ具合が明らかに違います。基本のリズムをJeremy Staceyに任せて自分はあれこれ小道具を使った効果音を出すことに徹しているPat Mastelottoが面白過ぎます。ヴァイオリンソロの部分はもちろんサックスが代替。そして、この曲から3曲連続でJohn Wetton期の曲が繰り出され、会場はヒートアップしていくことになります。
Fallen Angel
アルバム『Red』の中でも最も美しいこの曲のイントロが流れたとき、ふと今は亡きJohn Wettonのことを思い出して涙が出そうになるほどの感動を覚えました。悲壮感漂う歌詞、叙情的なボーカルライン、3拍子と4拍子をシームレスに行き来する魔法のようなリズム。最高です。
One More Red Nightmare
続いて『Red』の中でも「Fallen Angel」の次に置かれたこの曲。原曲でのBill Brufordによる破滅的なドラムパートを3人のドラマーが順送りで自由に叩きまくるのが見どころでしたが、やはり聞く側の脳内に原曲の刷り込みがあるせいか、3人がかりでもBill Brufordを超えられているようには見えませんでした。
Moonchild
ここでこの曲がくるのか……とちょっと驚き。Robert Frippのサステインの効いたギター、上手と下手の2人のドラマーが交互に叩く特徴的なシンバルフレーズ。原曲後半のフリージャズ風パートの代わりにメンバーそれぞれのソロが用意されており、Tony Levinがアップライトベースを弓で激しくダークに引き倒すソロを見せれば、Robert Frippはワウやファズを効かせたギターの持続音。さらにJeremy Staceyのリリカルなピアノソロ。次は誰のソロだろうと思った途端、ドラムのイントロが入って「The Court of the Crimson King」に移りました。
The Court of the Crimson King
原曲にほぼ忠実な演奏ですが、3人のキーボードが音を重ねてのメロトロンの洪水は圧巻。ギターのアルペジオはJakko Jakszykが弾き、Robert Frippはもっぱらキーボードに専念しています。フルートのソロも美しく、初めてこの曲を聴いたときの身が震えるような感動を思い出しました。演奏は終盤のブレイクからコーダの部分まで完全再現しており、最後のトーンクラスターはRobert Frippが両肘をキーボードに押し付けぐちゃぐちゃにして出していました。
Starless
メロトロンの冷え冷えとしたイントロから始まる前半の演奏は、最高です。Jakko Jakszykのボーカルも情感がこもり、中間のギターの単音が延々続くパートに入ると、ここまで淡々と白色光でバンドを照らしていた照明が徐々に暗く・赤く染まっていき、音数も音圧もどんどん上がってきます。そしていよいよ後半の疾走部……なのですが、残念ながらまったくスピードが足りません。この日の演奏の中で、ここだけははっきりと不満の残るものとなってしまいました。
21st Century Schizoid Man
アンコールはプログレ史に燦然と輝くロックナンバーである「21世紀の精神異常者」。「Starless」での不満を吹き飛ばすような快演でした。イントロの効果音でそれと察した聴衆から大きな歓声が上がり、そして一気にあの有名なリフへ。ボーカルパートが終わってインストパートへの導入部のスネア三連打を3人のドラマーが分け合った後、ツインギターでの息のあったソロ、さらに渾身のサックスソロの背後でTony Levinが鬼気迫る表情での激しいランニングベースを聴かせ、サックスソロが終わってTonyとMelが笑顔を交わしている間に、Gavin Harrisonがエレクトロニックパーカッションも交えた長大なドラムソロ。Gavinがツインペダルの高速連打を伴う重戦車状態になったところにRobert Frippのギターの持続音がクレッシェンドで滑り込んで、全楽器ユニゾンの決めフレーズが炸裂しました。最後のメインリフに戻ったときには、周囲は総ヘッドバンギング状態。曲が終わった瞬間にさっと3人のドラマーが立ち上がって、ショウの終了を告げました。
前半が攻撃的な選曲、後半が懐メロ期待に応える構成とメリハリのついたセットリスト。これだけの音楽性と技術を持つミュージシャンを揃えているだけに、安定しきった演奏の中に高度なアレンジが散りばめられて、50年間というバンドの歴史を「回顧」するのではなく「参照」した新しい音楽体験を供給していました。中でもトリプルドラムやサックスの自由度が、どの曲にも新しい命を吹き込んでいたように感じられましたが、これは取りも直さず、2013年にRobert FrippがKing Crimsonをこの陣容で再始動しようとしたときの構想が成功していたということに他なりません。
しかし、Jeremy Staceyに加えRobert Frippも積極的にキーボードを弾いていたこの編成において、さらに専属のキーボードプレイヤーは必要だったのか?という疑問もなきにしもあらず。この点に関しては、開演前に買い求めたプログラムに書かれていた「キング・クリムゾン2018の7か条」が考察のヒントを与えてくれているかもしれません。
- キング・クリムゾンがすべての人の喜びとなりますように。私も含め。
- もしあなあたが役割を果たしたくなかったとしたら別にかまわない!誰かに振ってください。人手はじゅうぶんに足りています。
- すべての音楽は新曲だ。それがいつ書かれたとしても。
- もし音に迷ったら、C#を弾いてみよう。
- もし拍子に迷ったら、5拍子、もしくは7拍子で。
- もし何も弾けなくて困ったら、機材を増やせ。
- それでもまだ迷っていたら、何も弾くな。
Robert Fripp、Tony Levin、Mel Collinsの3人はすでに70歳に達していますが、彼らが牽引するこのバンドはどこまで進化を続けられるのか?前回の来日のときは「これが見納めか」と思ったものですが、こうしてあっさりその予想を覆されてしまうと「また次もあるのではないか」と思えてしまいます。

ミュージシャン
| Robert Fripp | : | guitar, keyboards |
| Jakko Jakszyk | : | guitar, vocals |
| Mel Collins | : | saxophone, flute |
| Tony Levin | : | bass, chapman stick, backing vocals |
| Pat Mastelotto | : | acoustic and electronic percussion |
| Gavin Harrison | : | acoustic and electronic percussion |
| Jeremy Stacey | : | acoustic and electronic percussion, keyboards |
| Bill Rieflin | : | keyboards |
セットリスト
- Banshee Legs Bell Hassle ("Drumsons Vibrate Goodwill")
- Indiscipline
- The ConstruKction of Light
- Epitaph
- Neurotica
- The Letters
- Radical Action (To Unseat the Hold of Monkey Mind)
- Meltdown
- Radical Action II
- Level Five
- Islands
--- - CatalytiKc No. 9 ("Drumsons Emanate Compassion")
- Peace: An End
- Discipline
- Cirkus
- Larks' Tongues in Aspic, Part 2
- Fallen Angel
- One More Red Nightmare
- Moonchild
- The Court of the Crimson King
- Starless
--- - 21st Century Schizoid Man
これらの曲をディスコグラフィーに当てはめてみると、次のとおりになりました。
| 発表年 | アルバム | 曲セットリストの番号 |
|---|---|---|
| 1969 | In the Court of the Crimson King | 4,19,20,22 |
| 1970 | In the Wake of Poseidon | 13 |
| 1970 | Lizard | 15 |
| 1971 | Islands | 6,11 |
| 1973 | Larks' Tongues in Aspic | 16 |
| 1974 | Starless and Bible Black | |
| 1974 | Red | 17,18,21 |
| 1981 | Discipline | 2,14 |
| 1982 | Beat | 5 |
| 1984 | Three of a Perfect Pair | |
| 1995 | THRAK | |
| 2000 | The Construkction of Light | 3 |
| 2003 | The Power to Believe | 10 |
| 2016 | Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind | 1,7,8,9 |
| 2018 | Meltdown: Live in Mexico City | 12 |
今回のツアーでは日替わりでセットリストが変わるため、この表だけで選曲の傾向を見出そうとすることは危険ですが、2015年のツアーのときにも話題になったようにAdrian Belew期の楽曲が比較的少ない(しかし、2015年に比べれば多い)ことについては、以下の事情があったようです。
- 2013年のKing Crimson再始動に際し、Robert Frippがメール1本でAdrian Belewをラインナップから外したために両者の間に確執が生まれ、新ラインナップではAdrianが書いた曲は演奏しないという「紳士協定」がなされた(しかし、その後両者は和解した)。〔出典:Gizmodrome来日前の「BARKS」のAdrian Belewに対するインタビュー〕
- イギリス人であるJakko Jakszykは、アメリカ人であるAdrian Belewの語彙や発声を元に歌うことに抵抗があった(しかし、例えば「Indiscipline」は原曲の歌詞にJakkoがオリジナルのメロディーをつけてこの問題を解決した)。〔出典:本ツアーに伴う「rockin'on」のJakko Jakszykに対するインタビュー〕