David Byrne's American Utopia
2021/05/31
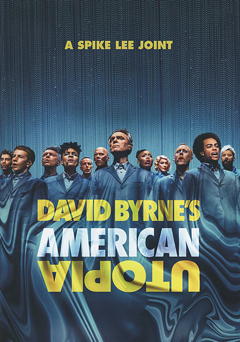 渋谷のホワイト・シネクイントで『American Utopia』。Talking HeadsのフロントマンだったDavid Byrneが多国籍のミュージシャンやダンサーと共にブロードウェイの舞台で繰り広げるショウをSpike Lee監督が映像化したこの作品はもちろん映画なのですが、その臨場感が素晴らしかったので、ここでは「音楽」にカテゴライズして記録します。
渋谷のホワイト・シネクイントで『American Utopia』。Talking HeadsのフロントマンだったDavid Byrneが多国籍のミュージシャンやダンサーと共にブロードウェイの舞台で繰り広げるショウをSpike Lee監督が映像化したこの作品はもちろん映画なのですが、その臨場感が素晴らしかったので、ここでは「音楽」にカテゴライズして記録します。
Talking Headsはこれまでの自分の音楽ライブラリの中になかったのですが、それはNYポストパンクというレッテルを敬遠していたせいでもあるし、彼らが存在感を示していた1980年前後の自分はRushの演奏能力至上主義に傾倒していたせいでもあります。しかし、この3日前の日本経済新聞夕刊の文化欄に掲載されたこの映画の紹介記事がいたく心に響き、それならばと予約をして観に行くことにしたのでした。
ショウはTalking Headsの曲やソロになってからのDavid Byrneの曲などを合計21曲連ね、その合間にDavid Byrneの語りを交える構成で、全員の全ての動きはあらかじめ振り付けられたもの。リードボーカルと時にギターをDavid Byrneが務めるほか、男女2人のダンサー兼シンガー(うち男性はJokerのようなメイク)、6人のパーカッション、1人ずつのベース、ギター、キーボードという構成です。やや狭く正方形に近い長方形の舞台は、三方を重量感のあるスダレのようなカーテンで覆われ開口部が客席に向いており、ミュージシャンたちはスダレの間から自由に出入りできます。そしてほぼ素足で動き回る彼らの出立ちはライトグレーのスーツ上下にさらに明るいグレーのシャツで統一され、このことが照明の効果を最大限に引き出します。
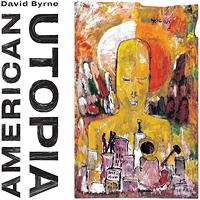 オープニングは2018年にリリースした『American Utopia』から、クリスタルのオーロラが立ち上がっていくような荘厳な雰囲気の中で脳の模型を片手にDavid Byrneが1人で歌い上げる「Here」。その曲調にPeter Gabrielが『Secret World Live』で聞かせた「Come Talk to Me」を連想しているうちに、"connection" や "neurons" といった単語を散りばめながら大脳の各領域の機能と共に「ここ」でこれから展開されることの意味を暗示したDavid Byrneは、続くMCで赤ん坊の神経細胞のつながりは大人のそれよりも多いことを指摘し、人は成長するにつれより愚かになりやがて愚かさの高原に辿り着く、と聴衆を笑わせました。続いて世界のありようを懐疑的に眺める「I Know Sometimes a Man Is Wrong」、擬人化した政府を主人公とする「Don't Worry About the Government」と穏やかでシニカルな曲が重なるにつれ、ステージ上に登場するミュージシャンの数は徐々に増え、リズムが力を増していきます。
オープニングは2018年にリリースした『American Utopia』から、クリスタルのオーロラが立ち上がっていくような荘厳な雰囲気の中で脳の模型を片手にDavid Byrneが1人で歌い上げる「Here」。その曲調にPeter Gabrielが『Secret World Live』で聞かせた「Come Talk to Me」を連想しているうちに、"connection" や "neurons" といった単語を散りばめながら大脳の各領域の機能と共に「ここ」でこれから展開されることの意味を暗示したDavid Byrneは、続くMCで赤ん坊の神経細胞のつながりは大人のそれよりも多いことを指摘し、人は成長するにつれより愚かになりやがて愚かさの高原に辿り着く、と聴衆を笑わせました。続いて世界のありようを懐疑的に眺める「I Know Sometimes a Man Is Wrong」、擬人化した政府を主人公とする「Don't Worry About the Government」と穏やかでシニカルな曲が重なるにつれ、ステージ上に登場するミュージシャンの数は徐々に増え、リズムが力を増していきます。
どこまでも怠惰で不活性な現代人の暮らしぶりをシニカルに歌うX-Press 2の「Lazy」に続き、人とのつながりを持つのにアプリが必要な人もいればそうではない人もいるが人を見ることは自転車(David Byrneは旅先に自転車を持参し都市を走る趣味を持つ)よりも美しい夕景色よりもポテトチップスの袋よりも素晴らしいと語られて、可愛らしいリフに乗り牧歌的に歌われるナイーブなラブソング「This Must Be the Place (Naive Melody)」。一転して1980年台King Crimsonに通じる強烈な16ビート「I Zimbra」(Talking Headsの原曲ではRobert Frippが参加)はダダイストHugo Ballの詩を用いていますが、この曲を歌う前にDavid Byrneは同じダダイストKurt Schwittersのナンセンス音響詩「Ursonate」を素っ頓狂な口調でひとくさり歌って「これが40分続く」とやってから、ファシズムとナショナリズムの時代に個人の独立を貫こうとした彼らに敬意を表しました。
"He's alright" と繰り返しながらどうして大丈夫なのかさっぱりわからない「Slippery People」に続き、かつてTalking Headsが最初に契約をとれたときに支払われたささやかなお金でDavid Byrneがソニーの小さなカラーTVを買ったエピソードから、ダークでインダストリアルな打込みの16ビートと大ノリ2ビートのバスドラ&スネアが同期する「I Should Watch TV」へ( "Touch me and feel my pain" が刺さる)。続いて「皆が我が家にやってくる・誰も家に帰ろうとはしない」と歌う「Everybody's Coming to My House」についてDavid Byrne曰く、この曲をデトロイトのハイスクールの合唱部が歌うと歓迎の雰囲気になるが、自分が歌うと微妙な居心地の悪さ(本当は帰って欲しい……)が漂う。もちろん前者がいいのだが、残念ながら自分はこういう人間だから(Unfortunately, I am what I am.)。ここで湧き起こった拍手に彼は「その拍手はどういう意味?」と軽くむっとして見せてさらなる笑いを獲得していましたが、この話と共にバンドメンバーが多国籍であること、David Byrne自身もスコットランドからの移民であることが語られれば、この曲の「My House」が何を意味しているかは明らかです。
TVエバンジェリストの力強い口調を借りているのに自分の存在や居場所についての不安をかき立てるDavid Byrneの語りと底抜けに明るいアフリカンコーラスが交互に繰り返される「Once in a Lifetime」の後には、いにしえの『ジャングル大帝』(冨田勲)を思い出すパーカッションのパターンと "It is just a house, not a home" の一句が効いてくる「Glass, Concrete & Stone」を経て、ユーモアを交えつつ選挙での投票率の低さ(地方選挙に至っては20%にすぎないといって客席の1/5を照らす)や投票者の平均年齢の高さを数字で示して聴衆の認識レベルを引き上げておいてから、一転してラテンテイストが能天気な「Toe Jam」へ。
「Born Under Punches (The Heat Goes On)」は、本当にステージ上で演奏しているのか?というもっともな疑念を晴らすためにメンバーを1人ずつ紹介しながら音を重ねていく演出が施されていましたが、そこで歌われているのは息詰まるような圧迫感。そこから「I Dance Like This」の破滅的なビートで客席に抑圧を加えた上で、一転して穏やかな演奏の上に容赦のない暴力描写を歌詞に載せる「Bullet」へ。この曲が終わり、とまどいの混じった拍手を聞きながらDavid Byrneはその場を取りなすように「舞台上から本当に必要なもの以外を取り除いていったら、残るのは我々と皆さん。それがこのショウだ」と宣言した上で親しみやすいメロディーと少々シュールな歌詞を持つ「Every Day Is a Miracle」。さらにダンサブルで摩訶不思議な内容の「Blind」「Burning Down the House」が演奏されて、客席は一転して大盛り上がり。
しかしこのショウの白眉となったのは、白人である自分が歌うことの可否を作者Janelle Monáeに確認し快諾されたというプロテストソングにしてレクイエム、さらにこの不完全な世界だけでなく自分自身の変革の可能性を歌う歌でもあると前置きがなされた上で歌われた「Hell You Talmbout」でした。全員がパーカッションを持ち、黒人差別の犠牲となって命を落とした人々の名前を連呼し "say his name" と客席に迫るそのエネルギーはスクリーン越しであっても圧倒的ですが、この一体感は歌う側と聴く側の双方にゴスペルの下地がないと出せないかも。そしてここでは例外的に、舞台上だけでなく犠牲者の写真(と家族の姿)が映し出される演出が施されていました。
最後に、冒頭で語られた脳の話題が再度提示され、"connections between all of us" を取り戻すことへの希望をアカペラで朗々と歌い上げる「One Fine Day」が歌われてから、おそらくはアンコール曲として演奏されたのであろう「Road to Nowhere」でマーチングバンドと化した演奏者たちが客席を一周し終えたところで、ほぼ100分に及んだこのショウは終了しました。
 一貫したストーリーの中に新旧の楽曲の歌詞がパズルのピースのようにがっちりとはまり、演奏もパフォーマンスも精緻に組み立てられて緊密な構成を持った魔法のようなショウでした。Talking Headsの楽曲はもともと無機的なリズムがミニマルに続く曲が多い印象ですが、このショウでは多彩なパーカッションが導入されたことでリズムに躍動感が生まれ、新しい生命が吹き込まれていたと感じました。David Byrneの歌声も60代後半とは思えない張りと伸びやかさを保っていましたが、終演後にバックステージへとキャストの姿を追ったカメラはそこで彼らがショウの出来にいたく興奮している様子を記録していました。プロのミュージシャンでありダンサーである彼らがここまでハイになっているという事実は、このショウが一方的なパフォーマンスではなく観客との "connection" の上に成り立ち、そしてそのことに成功したと彼らが感じたことを物語っているのでしょう。
一貫したストーリーの中に新旧の楽曲の歌詞がパズルのピースのようにがっちりとはまり、演奏もパフォーマンスも精緻に組み立てられて緊密な構成を持った魔法のようなショウでした。Talking Headsの楽曲はもともと無機的なリズムがミニマルに続く曲が多い印象ですが、このショウでは多彩なパーカッションが導入されたことでリズムに躍動感が生まれ、新しい生命が吹き込まれていたと感じました。David Byrneの歌声も60代後半とは思えない張りと伸びやかさを保っていましたが、終演後にバックステージへとキャストの姿を追ったカメラはそこで彼らがショウの出来にいたく興奮している様子を記録していました。プロのミュージシャンでありダンサーである彼らがここまでハイになっているという事実は、このショウが一方的なパフォーマンスではなく観客との "connection" の上に成り立ち、そしてそのことに成功したと彼らが感じたことを物語っているのでしょう。
2018年、つまりトランプ政権のただ中に逆説的なタイトルの『American Utopia』をリリースし、翌年に大統領選挙を控えた2019年にこのショウを実現したDavid Byrneの意図は明確です。エンドロールの中でも投票登録を促すメッセージが示されて、その意味ではこれはアメリカ人のアメリカ人によるアメリカ人のためのショウであり映画なのですが、全編を通じて維持されるユーモアのセンスと共に、生身のミュージシャンによる溌剌としたビートとひねりの効いた歌詞が絡み合ってスクリーンを突き抜けてくる社会変革へのその熱気は、今の日本人も受け止めておきたいもの。
若い頃のDavid Byrneのパフォーマンスに見られた性急さや病的な要素は影を潜め、ストレートに聴衆に語り掛け唱和を求めるその姿は力強く希望に満ち、Talking Headsの曲であってもむしろ40年前より説得力が増していました。これが本当に『Stop Making Sense』(1984年のTalking Headsのステージの映像化作品)で偏執的な表情や痙攣パフォーマンスを見せビッグスーツを着ていた彼?あるいは、これが本当に『ベストヒットUSA』にゲスト出演して小林克也と話が噛み合わずひんやりした空気をスタジオに充満させていた彼?この『American Utopia』でのDavid Byrneなら、私は好きになれそうです。しかし、たとえ(私のように)Talking HeadsやDavid Byrneの音楽を聴いたことがない人であっても、この映画は十分に楽しめ、そして最後には感動すること請け合い。音響の良い映画館で観ることを強くお勧めします。
ちなみに、ホワイト・シネクイントは音量・音質共グッドでした。
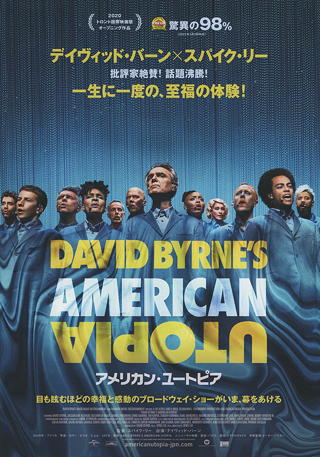 |
 |
ミュージシャン
| David Byrne | : | vocals, guitar, percussion |
| Jacquelene Acevedo | : | percussion |
| Gustavo Di Dalva | : | percussion |
| Daniel Freedman | : | percussion |
| Chris Giarmo | : | dance, vocals |
| Tim Keiper | : | percussion |
| Tendayi Kuumba | : | dance, vocals |
| Karl Mansfield | : | keyboards |
| Mauro Refosco | : | percussion |
| Stephane San Juan | : | percussion |
| Angie Swan | : | guitar |
| Bobby Wooten III | : | bass |
セットリスト
*=Talking Heads / **=David Byrne『American Utopia』
- Here **
- I Know Sometimes a Man Is Wrong / Don't Worry About the Government *
- Lazy
- This Must Be the Place (Naive Melody) *
- I Zimbra *
- Slippery People *
- I Should Watch TV
- Everybody's Coming to My House **
- Once in a Lifetime *
- Glass, Concrete & Stone
- Toe Jam
- Born Under Punches (The Heat Goes On) *
- I Dance Like This **
- Bullet **
- Every Day Is a Miracle **
- Blind *
- Burning Down the House *
- Hell You Talmbout
- One Fine Day
- Road to Nowhere *