The Return of Emerson, Lake & Palmer
2023/12/13
EXシアター六本木で「The Return of Emerson, Lake & Palmer」。Emerson, Lake & Palmer(以下「ELP」)の3人のうちキーボードのKeith Emersonとベース、ギター、ボーカルのGreg Lakeはすでに鬼籍に入っていてドラマーのCarl Palmerだけが存命ですが、このショウは3人揃ってステージに立った1992年10月のロイヤル・アルバート・ホール(以下「RAH」)でのライブの際に5台のカメラによって収録した映像と楽器ごとに録音した音源を活用し、ステージ後方のスクリーンにKeithとGregの姿を映し出しながら当時の2人の音にCarlがドラムを合わせたり、あるいはステージ上のギタリストとベーシストとの3人のリアルな演奏でELPの曲を再現するものです。
フライヤーの売り文句としては、
エマーソン、レイク&パーマーが27年振り、4度目の来日公演を12月に開催!
結成50周年の時を超えてステージで奇跡の共演!
ということですが、私がまだ洋楽に親しんでいなかった1972年の初来日(雷雨の後楽園球場と暴動の甲子園球場)を除けば、ELPの来日は再結成後の1992年と1996年しかなく、そのいずれもなぜか見逃していたので、変則的な構成ながらこの機会を逃してはいけないと思ってチケットを手に入れました。
日本での公演は前日とこの日の2日間、東京公演のみ。いつもならsetlist.fmとYouTubeでセットリストや演奏ぶりの予習をするのですが、今回はむしろサプライズを楽しみたかったので、あえて予備知識なしで当日を迎えました。

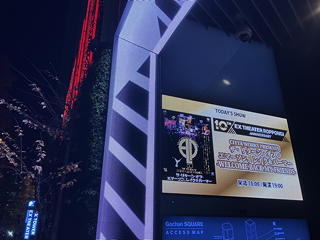
初めて訪れたEXシアター六本木は10年前にテレビ朝日が開設したライブハウス兼用劇場だそうで、六本木駅から西麻布方向に徒歩数分。武道館公演なら必ず見かける「チケットあるよ」のおじさんたちの姿は見当たらず、すんなり建物の中に入ることができました。入場に際してドリンク代500円が別途必要なのは、この公演のプロモーターであるチッタワークスの本拠地クラブ・チッタと同じです。


グッズ売場には長蛇の列ができていましたが、開演1時間近く前に入ったので十分ゆとりを持って目当ての「完全永久保存版『ELP公演記念BOOK』(B4サイズ全28ページ・フルカラー)」をゲットしてシアタナー内に入りましたが、この公演に気づくのが遅かったためか座席は2階席(建物のフロアとしては地下1階)の最後列となってしまいました。さすがに遠いとは思うものの、後ろを気にせずじっくりとステージを見下ろすことができるこの位置も悪くはありません。さらに、あらかじめのアナウンスでは「ファンファーレ」の演奏時のみスマホによる写真撮影が可能(動画は禁止)ということなので、かえってシャッターチャンスを逃すまいと身構える必要もなく演奏に集中できそうです。
BGMの少年合唱団による聖歌を聞きながら観察してみると、ステージ上は中央にCarlのツーバス・ツータム・ツーフロア・ツードラ(!)の立派なドラムセットが鎮座しているものの、下手側のギタリストPaul Bielatowicz、上手側のベーシストSimon Fitzpatrickのそれぞれの立ち位置は足元も含めてさっぱりした風情。それよりも3人の背後に並ぶスクリーンが大きく、中央にはCarlがこれまで参加してきた作品のアルバムジャケット(ELPと共にAsiaが目立ちます)が並び、左右からは上側に「WELCOMEBACK MY FRIENDS」、下側に「50 THE RETURN OF EMERSON, LAKE & PALMER」の文字を伴うELPのロゴが客席を睥睨しています。
定刻を5分ほど過ぎたところで照明が落ち、まずCarlの姿が映って、これはKeithとGregという2人の偉大なミュージシャンに対するdedicationであるという趣旨の説明がなされた後、TVドラマっぽい映像やアニメ「ザ・シンプソンズ」がELPの名前を連呼し、さらには青い光の明滅と高らかなシンセ音と共にELPのオーケストラ帯同ツアーで使用されたトレーラー(屋根に3人それぞれの名前)が映し出された後、3人のミュージシャンがステージ上に登場して拍手で迎えられました。
以下、演奏順に各曲の印象などを記します。曲名の後の記号は演奏形態を示しており、●=映像の中のELとステージ上のP、○=ステージ上の3人、◎=映像の中のELとステージ上の3人です。
Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2〔●→○〕
MoogのSampe & Hold効果音からドッカンドッカンとドラムが入って、まずはワンコーラスを映像と音源と共に演奏した後、RAHではオルガンソロに入らずに「Tarkus」に移っていたのですが、ここからリアルの3人での演奏になりました。しかもオルガンソロのパートはSimonの6弦ベースにエフェクトをかけてそれらしい音で再現し、その後のギターのテーマ以降はシンセもオルガンもPaulがギターで出すといった具合。ついでに締めのボーカルもPaulでしたが、この辺りから3人のリズムがばらばらになるというおまけ付きでハラハラしました。
Hoedown〔○〕
コープランド作曲の「Hoedown」は、ELPの3枚組ライブ盤『Ladies and Gentlemen』の1曲目としてファンにはとりわけ馴染みがある曲。これはリアル演奏で、冒頭のシンセサイザーのポルタメントはPaulがフットペダルで出し、背後のオルガンはギター。その後の速い単音フレーズになると比較的ナチュラルなギター音になっていましたが、途中にこれまたナチュラルな音でのベースソロが入ってきたのが斬新です。さらにスタジオバージョンで終盤に引用されていた「Turkey in the Straw」をギターとベースがユニゾンで弾いてエンディングに持ち込みましたが、なにせCarlがツーバスでドカドカ踏み続けるので凄い迫力でした。
ちなみにCarlはELPではオーソドックスなワンバスでしたし、ツーバスのセットになったAsiaでもファーストアルバム(1982年)の頃はツーバスの演奏がこなれていない(例えば「Sole Survivor」のアウトロ)印象でしたが、しばらく後のPat Thrallをギターに迎えた時期のライブ(1990年)を見てツーバスを見事に活かしていたことに驚いた記憶があります。
Knife-Edge〔◎〕
演奏の前にステージの前にCarlが出てきて聴衆は大喜び。その彼がベーシストとギタリストを紹介した後、曲名を紹介してから始まったのはELPのデビューアルバムから「Knife-Edge」(原曲はヤナーチェク「シンフォニエッタ」)。ベース主体の静かなパートではKeithとGregの映像にCarlが印象的なシンバルフレーズを重ね、オルガンが入って音量が上がるとギターとベースも音を重ねます。キーボードの音をギターが出しているのかな?とも思いましたが、オルガンのグリッサンドが出てきたことでRAHの音源が主体であることが確認できました。その後にKeithがピアノを弾くところでギターがオブリガートを乗せていましたが、おおむね「ELP」としての演奏だったと見てよさそう。
Take a Pebble〔CarlとSimonのデュオ〕
ここでSimonがチャップマン・スティックに持ち替え、「Take a Pebble」冒頭のピアノ弦を直接弾くあのイントロをきれいなクリーントーンで演奏。その後はスティックの特性を活かしてボーカルのラインと伴奏とを一人で演奏し、そこにCarlがシンバルとタムを優しく重ねて原曲の雰囲気を出しました。さらにベースとピアノの絡みもスティックで再現した後、原曲ではアコースティックギターだけになる緩徐部ではアタックを消しサステインを利かせたスペイシーな音でムードを作ると、クリーントーンに戻ってCarlのハイハットと共にリズミカルなパターンを作り、そこへ重ねてきたのが予想外のプロコフィエフ「キージェ中尉」から「トロイカ」。これはGregのソロ曲「I Believe in Father Christmas」のアウトロで引用されていたもので、ここではスティックがクリーントーンに牧歌的なパンパイプ風の音を混ぜていたようでした。
Benny the Bouncer〔○〕
Carl曰く、Gregはステージでは歌おうとしなかったがレコーディングされた曲は素晴らしかったので自分で歌う(超訳)と紹介し、自らボーカルをとってステージ上の3人でこの曲を演奏しました。Carlのボーカルはお世辞にも上手とは言えませんが原曲自体が荒々しい雰囲気で歌われているのでむしろこの曲にぴったりですし、ブラシで叩くスネアが作る疾走感もすてき(ただしややゆっくり目)。そして間奏のピアノソロの部分は前半をベース、後半をギターが再現しました。
ところでステージ上のボーカルマイクは、ギタリストのところに一つ、ドラムセットのところにCarlが歌うためのものが一つ、そしてドラムセットの前に一つあって、CarlがMCをするのに自分の手元のマイクではなくわざわざステージ前方に出てくるのが微笑ましかったのですが、この歌の終盤でSimonがその前方のマイクの方に出てきたと思ったら、BennyとSidneyの喧嘩の結末に人々が息を呑む「The end of a Ted?!」のワンフレーズだけ3人で声を合わせるユーモラスな一幕がありました。
Creole Dance〔映像の中のKeithのピアノソロ〕
ショウの実現にあたりKeithの家族からの希望があって彼のピアノソロを演目に加えたという説明があり、ヒナステラの「Creole Dance」がRAHでのKeithの演奏をそのまま映像と音で流しました。後方3面のスクリーンのうち左右はライブでの演奏の様子を映していましたが、中央ではKeithのプライベート(彼の家や趣味の飛行機操縦)やカリフォルニア・ジャムでの縦回転ピアノなどが映っていました。
Tarkus〔○〕
Simonが再びスティックを構えて、これまた予想外だった「Tarkus」全曲演奏。冒頭のAh音がクレッシェンドして5拍子パターン(ただしこれもゆっくり目)に入った後は完全にステージ上の3人による演奏であり、このショウの白眉ともなりました。「Eruption」で目まぐるしくフットペダルを踏み替えながらPaulがギターで出すTarkusの叫び、リズムを断ち割るCarlのドラ(ここで1階席から歓声が上がってほしかった!)、「Stones of Years」では残念ながらあまりに平板なPaulの歌にGregのボーカルの偉大さを思い、打って変わって「Iconoclast」では引き締まったリズム隊を聞くことができ、続く「Mass」はボーカルに抒情性が求められないのでPaulの歌唱も馴染み、「Manticore」の高速9拍子でのカウベルを交えた複雑なドラムパターンに目を見張り、「Battlefield」を短縮版として飛び込んだ「Aquatarkus」はCarlのぐいぐいと強烈にドライブするドラムにSimonのスティックが奇天烈なシンセ音で絡んで、最後は冒頭の「Eruption」に回帰して大団円です。演奏が終了した瞬間、客席からこの日一番の大きな歓声と拍手が上がりました。
Trilogy〔○〕 / Guitar Solo
まず「Trilogy」は冒頭の高いストリングス系の音をベースがオクターブ下げてヴァイオリン奏法で弾き、続くピアノ部はエコーが効いた美しいクリーントーンのギター。Gregのボーカルラインをベースがなぞり、Carlもシンバルロールをひそやかにかぶせると、ギターの演奏は聞き慣れたドビュッシーに移り、CarlとSimonは袖に下ります。ここからPaulのソロ演奏による「月の光」となるのですが、これは彼のソロアルバム『Preludes & Etudes』にも収録された曲で、両手を組み合わせた巧みなタッピングによるおおむね原曲どおりの演奏の中に、部分的にギタリストらしい解釈による速弾きのアドリブが挿入されていました。
Carmina Burana〔○〕 / Drum Solo
再びステージ上にCarlとSimonが戻って、3人でおどろおどろしく「Carmina Burana」(作曲者はカール・オルフ)。シンバルと細かく軽いスネアを延々と叩く高速ドラミングは後の「Rondo」にも通じるもので、実際ELPの1997年のライブ音源(モントルー)では「Fanfare for the Common Man」の後に「Rondo」「Carmina Burana」とつなげていましたが、ここではCarlのドラムソロのイントロとして用いられました。10分ほども続いたそのドラムソロは相変わらず凄いのだかそうでないのだか(ドラマーでなければ)わからないながらも楽しいもので、こんなこともできるんだぞと言わんばかりにあらゆるパターンのスティック捌きでドラムセットの構成パーツをくまなく叩いた後に、バスドラをドカドカやりながら両腕を前に突き出す得意のポーズ。ここで彼の十八番であるTシャツ脱ぎが出てくることを期待した観客も多かったと思いますが、さすがに彼もこの年齢になると分別が出てきてそういう真似はせず、そのまま派手にドラを連打しました。
そういえば今から40年近くも前に読んだ音楽雑誌の中でBill Brufordがさまざまなドラマーについての感想を述べている記事を読んだことがあるのですが、その中にCarlについての言及があり、Billは「ロールの速さでは天下一品」と褒める一方で「ドラムソロでTシャツを脱ぐパフォーマンスはやめた方がいいと誰か言ってあげた方がいい」と皮肉っぽく語っていたことを思い出しました。
From the Beginning〔映像の中のGregとCarl+Simon〕
息をはずませながらもCarlはドラムセットの向かって右に設置されたコンガに向かい、Gregのギターとボーカル、Carlのコンガ、Simonのベースのトリオ演奏で「From the Beginning」。いつ聞いてもGregのアコースティックギターは音がきれいで惚れ惚れしますが、RAHでは彼一人の弾き語りだったのに対しここではコンガとベースが加わったことで原曲のアレンジにぐっと近づき、いっそう味わい深いものとなりました。
Paper Blood〔◎〕
1990年代の再結成ELPによる『Black Moon』から「Paper Blood」。PaulとSimonもステージ上で演奏していますが、音としてはRAHのKeithとGregの演奏が中心だったようです。したがってこちらもスクリーン上のKeithとGregの姿に目を凝らしていたのですが、ふと気づくとこの曲の中でGregは2種類のベース(WalとTune)を弾いています。おそらくRAHの演奏は2日間収録され、音源はどちらか一つで通すとしても映像の方は2日分のストックの中から都合がいいところを抜き出して合成したのでしょう。
ついでに書けば、せっかくELPの3人が揃い踏みするのだから3面あるスクリーンのそれぞれに1人ずつ映して映像面でもELPが同時に見られるようにすればいいのにと思いたくなりますが、実際には左右のスクリーンは同じ映像が投影されており、したがって一度に映るのはKeithかGregのどちらか片方だけ。あくまで推測ですが、KeithとGregの2種類の映像はあっても、それぞれを編集した上に完全にシンクロさせて投影することに困難(またはリスク)があったのではないかと思われます。
Lucky Man〔◎〕
スクリーンの中のGregのギターとボーカルで始まり、ステージ上のPaulとSimonが控えめにギターとベースを重ね、そしてこの曲を特徴づけるKeithのアウトロのシンセサイザーソロ。ポルタメントを効かせた高音部をオルガン上のキーボードで弾き、間に差し挟まれる重低音を正面側のフットペダルで出すKeithの姿が大写しになりました。もしかするとこの曲に限ってはKeithとGregが左右に投影されていたかもしれない(海外での公演動画にそういう場面がありました)のですが、気づきませんでした。
それにしても、サビの「Ooh, what a lucky man he was」を周囲の誰も一緒に歌わなかったのは寂しかったな。Gregはギターを弾きながら「Sing along」と言っていたし、スクリーンの中のKeithも客席を指差しながらGregに合わせて自分でも歌っていたのに(私は歌いました)。
Fanfare for the Common Man / America / Rondo 〔●→◎〕
「The Greatest Rock Keyboard Player Ever」であるKeith Emersonをフィーチュアした曲だ、とCarlが紹介して、ステージ上はCarlだけになり、スクリーンの中のKeithとGregとの3人で最後のメドレー。曲はコープランドの「Fanfare for the Common Man」からバーンスタインの「America」を経てブルーベックの「Rondo」へ、さらにハチャトゥリアンの引用へと進み、映像の中のKeithは例によってHammond L-100を相手にグリッサンド祭りやロデオを繰り広げ、ナイフを鍵盤に刺して音をホールドしてからスプレーペンキで壁にELPのロゴを描くと、助走をつけてオルガンを飛び越してその下敷きになりながら逆さバッハ。そうした迫力満点の映像をリアルに演奏しているCarlもにこにこしながら横目で見ていましたが、ついに曲が終焉を迎えようとするときにPaulとSimonもステージに戻ってきて、最後のキメに加わりました。
全ての曲の演奏を終えたステージ上の3人が客席に手を振って舞台袖に下がった後に、スクリーン上ではフットボールのハーフタイムショーらしき情景の中でマーチングバンドが隊列を次々に変えながら「Karn Evil 9」を演奏し、そしてアンコールはないままに客電が点灯しました。その後もしばらくは手拍子を続ける観客が少なくありませんでしたが、聴衆の多くはCarlが全てを出し切ってステージを去っていったことを理解していたようです。

さすがに現在73歳のCarlは風貌が晩年のCharlie Wattsに似てきたような気がしますが、ドラミングの方は相変わらず「ゴーストノートを入れるくらいならロールする」と言わんばかりの手数の多さで、客席の全員を笑顔にするショウマンシップ満載のドラムソロも交え、すばらしくエネルギッシュでした。それにしてもこのショウのニュースが伝わってきたときは誰しも、あのタイム感が奔放なCarlが既存の音源にテンポを合わせてドラムを叩くなどという芸当ができるのか?と思ったことでしょうが、蓋を開けてみればCarlは(もちろんPaulとSimonも)見事な仕事ぶりでした。また、まさかのCarlの歌も聴くことができてさらにハッピー。終演後のツイッター(X)を見ると「ありがとう、カール・パーマー」という声がいくつも見られました。
そうしたCarlの頑張りとは別に、つくづく思ったのはGregのボーカルの素晴らしさです。Keithが商業的に成功しているThe Niceを捨ててでも手に入れたかった「ゴールデン・ボイス」は、この日投影された1992年時点ではずいぶん低く太い方に変質していたはずですが、それでも歌の説得力は圧倒的。そしてこの時期には彼らの演奏能力はずいぶん落ちていたとGreg自身が彼の自伝で書いているのですが、映像で見るELPは凡百のバンドを軽々と凌駕するパフォーマンスを見せていましたから、これが全盛期だったらどういうライブだったのかと空恐ろしくすらなってきました。
ちなみに私のこれまでのライブ歴を振り返ってみると、Keithは彼のバンドとしての来日で2度、GregはあのJohn Wettonのピンチヒッターとして短期在籍したASIAで1度、そしてCarlはASIAのメンバーとして何度も見ているのですが、冒頭に記したとおり本家ELPのライブは未経験でした。まさか、こういう形でELPの3人がステージ上に揃うライブを見ることになるとは思っていませんでしたが、ラストの「Fanfare for the Common Man」以下の怒濤の演奏では、KeithとGregがあの世からステージの上へ本当に降りてきているような臨場感に目頭が熱くなりました。
そんなわけで最後に私からも一言、述べておきたいと思います。ありがとう、Carl Palmer!
 |
 |
ミュージシャン
| Carl Palmer | : | drums |
| Paul Bielatowicz | : | guitar, vocals |
| Simon Fitzpatrick | : | bass, chapman stick |
なお、Paul Bielatowicsがギターでオルガンやシンセサイザーの音を出していた仕掛けはこちらの動画でわかります。
セットリスト
- Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2
- Hoedown
- Knife-Edge
- Take a Pebble(プロコフィエフ「トロイカ」を含む)
- Benny the Bouncer
- Creole Dance
- Tarkus
- Trilogy / Guitar Solo(ドビュッシー「月の光」)
- Carmina Burana / Drum Solo
- From the Beginning
- Paper Blood
- Lucky Man
- Fanfare for the Common Man / America / Rondo
参考
- ELPの楽曲における引用に関して
- 福田陽氏『プログレを語ろう』(2023/12/15閲覧)