Pete Roth Trio featuring Bill Bruford
2025/06/25
ビルボードライブ東京(赤坂)でPete Roth Trio featuring Bill Brufordの1stショウ。開場16時30分、開演17時30分、終演は18時40分頃。ギタリストのPete Rothを中心とするG・B・Dsのジャズトリオですが、ポイントはドラマーがあのBill Brufordであることです。


Yes、King Crimsonという二大バンドでロック史に残る名盤を作ってきたBill Brufordは、我々の世代(のプログレファン)にとって特別な存在です。キャリアの初期こそロックドラマーとして名声を築いた彼ですが、最初からその志向はジャズに向いており、キャリアの後半は完全にジャズドラマー。しかし還暦を迎えた2009年(イギリス人に「還暦」という概念があるかどうかは不明ですが)に引退し、以後は学びと執筆の日々を送っていたと聞きます。

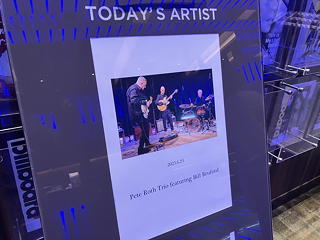
ところが、彼の心の中で何かが動いたらしく、2022年になって彼は突如スティックを握り直し、Pete Rothのトリオの一員としてシーンに復活してきました。かくしてイギリスやヨーロッパのジャズ・フェスティバルや、小さな劇場、クラブ、パブなどで演奏を重ねてきた彼らですが、さすがBillのネームバリューは極東においても絶大で、おかげで今回のツアーが実現したというわけです。そういう経緯であるためにこの日の観客の多くはPete Rothの名前と音楽には通じておらず、Bill Brufordの演奏をひと目見たくて(聴きたくて)この会場に足を運んでいただろうと思いますが、かく言う私も申し訳ないことにその一人です。
 |
 |
 |
 |
ビルボードライブ東京のカジュアル席は天井桟敷のように高いところからステージを見下ろす場所で、リーズナブルな金額で落ち着いて聴くにはこれでも十分ですが、この遠景だけではさすがに寂しいので、開演前に最下層のフロアに降りて楽器たちの写真を撮りまくりました。ドラムはシンプルな3点セットにハイハットとシンバルが3枚。うち1枚はサステインなしのパシャッとした音を出すエフェクトシンバルで、これが本番ではひときわ活躍していました。ギターはジャズらしくセミアコですが、ステージ上に置かれていたのはリザーブで、本番ではPeteが自ら抱えてきたギター1本ですべての曲をこなしており、一方、ベースはサンバーストが美しいFender Jazz Bass(フレッテッド)です。そして定刻5分前にうっすらスモークが漂いはじめ、定刻通りにステージ上に現れた3人はいずれも黒づくめ。Peteはキャップをかぶり、さらに彼とBillはメガネを掛けていて、聴衆からの拍手に笑顔で応えながらそれぞれの位置につきました。
最初に演奏されたのは、スペーシーなギターのコードがフェードインした後におもむろに力強いベースとドラムが加わるオリジナル曲「Full Circle」。このトリオのテーマ曲のようなものらしく、彼らのライブではオープニングナンバーとして演奏されることが多いようです。続いてBill Brufordの1997年のアルバム『If Summer Had Its Ghosts』からベースが気持ちよくスイングするタイトルナンバーが演奏された後、Pete RothによるMCが入って、ベースのハーモニクスが不穏な空気をかきたてるところから始まった三者の空間系インプロビゼーションの応酬が続きましたが、最後にギターによる聴き慣れたフレーズが出てきてこれがドヴォルザークの『新世界より』の変奏であることが判明しました。後のMCでPeteが、これはどう始まってどう進行するかが決まっておらずdangerousだということを述べていましたが、どうやら最後に「遠き山に日は落ちて」に着地するところだけが決まっていて、あとは毎回出たとこ勝負のようです。
次に、これはラテンのリズムだなと思ったらAntônio Carlos Jobim(「イパネマの娘」の作曲者)の「How Insensitive」で、その後半で展開したドラムソロが強烈でした。スナッピーを外したスネアとタムに細かいバスドラを加えた大胆な連打から始まり徐々に金物が加わって、ついにはギターとベースのリフの上であえてタガを外した大音量のドラミング。演奏終了後にはこの日一番の歓声と拍手が湧き上がりました。
ついでPeteが10歳の娘Graceのために書いたものの本人には気に入ってもらえなかったという穏やかで繊細なオリジナル曲「Dancing With Grace」を経て、10拍子の特徴的なベースリフから始まったのはBruford Levin Upper Extremities[1]の「Original Sin」です。B.L.U.E.の1999年のライブアルバムは持っているのにこの曲のことはすっかり忘れていましたが、ベースリフが作るダウナーな雰囲気の上にワウを効かせたギターと自在にリズムパターンを変えるドラムが重なって、とてもスリリングな演奏が繰り広げられました。
再びMCが入った後、ドラムによる刺激的なイントロからウォーキングベースが気持ちよいCharlie Parkerの「Billie's Bounce」が披露され、この曲のキメのフレーズが3人のユニゾンで演奏されてから、ちょっとトリッキーな9/4拍子のリフから始まったのはオリジナル曲「Looking Forward to Looking Back」です。ここではAllan Holdsworthを彷彿とさせるレガートでスピーディーなギターソロが聞かれ、さらに力強いアルペジオによる上行コード進行が曲を盛り上げた後に、いったん曲調が沈静化してギターとベースのデュオとなり、Billはドラムを離れて暗がりから二人を見守るかたちになりましたが、やがてBillが復帰したところからベースがメロディを奏でる3拍子となって、そのまましっとりと締め括られました。
トリオを讃える聴衆からの拍手の中で最後のMCが入り、アンコール的な位置付けで演奏されたのはその高速ぶりで知られるJohn Coltraneの「Mr. P.C.」。これをテーマリフできっぱりと締めくくって、1stショウのすべての演奏を終了しました。
終わってみれば、まずもってBill Brufordにびっくりです。シンプルなドラムキットから繰り出す音色の多彩さとリズム語彙の豊かさは圧倒的で、とても13年のブランクを経た76歳のドラミングとは思えません。事前に読んでいたインタビュー記事の中で彼は「自分にできることは何か?よりよいものを提供できるか?新しい何かを持ち込めるか?」を達成するのが自分の役割だと述べていましたが、私の見るところでは間違いなく、彼は「よいもの」「新しいもの」を高いレベルでこの日のステージに供給していました。いったい、あの「引退」はなんだったのか?
かたや、Pete RothのギターもMike Prattのベースも随所に聴きどころがあり、的確なトーンのセレクトと流麗なフレージングでBillと対等に渡り合い充実したライブを作り上げていたのですが、いかんせんBill Bruford目当てでジャズの作法に明るくないロックファンが客層のかなりの部分を占めていた(と思われる)上に、そのことを知ってか知らずかPAのバランスがドラム偏重だったため、たとえばせっかくのギターソロが終わっても拍手が出ず、途中でBillが演奏しながら客席にPeteへの拍手を促す場面が見られました。
彼らが日本の客層の特徴をこのステージでつかみ、2ndショウ以降では上手に聴衆との音楽的な対話を実現してくれているとよいのですが。

ミュージシャン
| Pete Roth | : | guitar |
| Bill Bruford | : | drums |
| Mike Pratt | : | bass |
セットリスト
- Full Circle
- If Summer Had Its Ghosts (Bill Bruford)
- From the New World (Antonín Leopold Dvořák)
- How Insensitive (Antônio Carlos Jobim)
- Dancing With Grace
- Original Sin (Bruford Levin Upper Extremities)
- Billie's Bounce (Charlie Parker)
- Looking Forward to Looking Back
- Mr. P.C. (John Coltrane)
脚注
- ^メンバーはBill Bruford(ds), Tony Levin(b), David Torn(g), Chris Botti(tp)。