NHK交響楽団(沼尻竜典 / 辻彩奈)
ショーソン / ラヴェル
2021/01/23
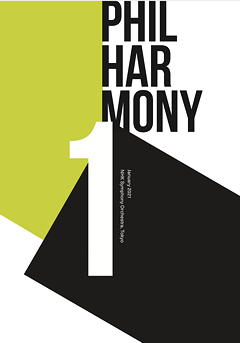 東京芸術劇場コンサートホールでNHK交響楽団の1月公演、指揮は沼尻竜典(敬称略・以下同じ)。エルネスト・ショーソン(1855-1899)とモーリス・ラヴェル(1875-1937)という2人のフランス人作曲家の作品を取り上げるプログラムで、ショーソン「詩曲」とラヴェル「チガーヌ」でのヴァイオリン独奏は2016年モントリオール国際音楽コンクール優勝の辻彩奈です。
東京芸術劇場コンサートホールでNHK交響楽団の1月公演、指揮は沼尻竜典(敬称略・以下同じ)。エルネスト・ショーソン(1855-1899)とモーリス・ラヴェル(1875-1937)という2人のフランス人作曲家の作品を取り上げるプログラムで、ショーソン「詩曲」とラヴェル「チガーヌ」でのヴァイオリン独奏は2016年モントリオール国際音楽コンクール優勝の辻彩奈です。
東京芸術劇場のプレイハウス(演劇)の方には何度も来ていますが、コンサートホールの方は初めて。世界最大級のパイプオルガンが設置されているとのことだったのでその姿を拝むことを楽しみにしていたのですが、残念ながら見ることはできませんでした。客席の埋まり具合は半分くらい?これも残念……と思っているうちにオーケストラ登場。短く刈った顎髭が個性的なコンサートマスター(白井圭)に導かれて音合わせがなされると、続いて拍手のうちに指揮者が客席に会釈しながら現れて、コンサートマスターと握手ならぬ肘タッチを交わしてから指揮台に登りました。
ラヴェル:組曲「クープランの墓」
原曲は全6曲のピアノ曲で、「墓」の言語tombeau
には個人を追悼する器楽曲という意味があるというとおり、各曲は第1次世界大戦で亡くなった知人たちに捧げられたもの。曲の着想源のひとつがラヴェルより200年前の宮廷作曲家フランソワ・クープラン作曲の「フォルラーヌ」の楽譜を含む記事にあり、バロック音楽の組曲形式を採用したことが、クープランの名前がタイトルに冠されている所以だそうです。ピアノ曲の初演と同じ1919年に2曲を省き順番も変えてオーケストレーションを施した管弦楽版がこの日の演目で、打楽器を含まない二管編成で演奏されます。
オーボエによる装飾的な12/16拍子のリフレインと美しい弦楽にのっけから引き込まれ、ハープのグリッサンドと共にキラキラと終わる第1曲「前奏曲」。浮遊する和声の響きの中で指揮者と木管楽器奏者がシンクロして肩を揺らす第2曲「フォルラーヌ」(17世紀ヴェネチアの舞曲)、オーボエとフルートが受け渡し合う旋律とこれらを包み込む弦楽が優雅でもあり郷愁をそそるようでもある第3曲「メヌエット」。そして第4曲「リゴードン」(プロヴァンス地方の古典舞踊)は、テンポを落とした木管のパートを真ん中に挟みつつハ長調の快活な弦楽で全曲を締めくくりました。
終曲後、指揮者から指し示されて聴衆の喝采を浴びたのは全曲にわたって美しい旋律を聴かせたオーボエ奏者。弦楽のダイナミズムの変化も、舞曲らしい躍動感が心地よいものでした。
ショーソン:詩曲 作品25
オーケストラの編成が変わり、続いて登場したヴァイオリニスト辻彩奈はえんじ色のドレス。曲はショーソンが亡くなる3年前(1896年)に、名匠ウジェーヌ・イザイ(1858-1931)のために作曲された一種の交響詩です。全体は弦楽器の苦手な変ホ短調をあえて採用し、後半に現れるホ短調に移調された主題を効果的に響かせているとのこと。
暗く立ち上がる和声から、情感のこもったヴァイオリン独奏による第一主題とこれを引き継ぐ弦楽。そして長く尾を引くホルンを従えて再び独奏を始めたヴァイオリンによる重音を多用した切ない響きが印象的です。第二主題で曲が進行し、ヴィオラがヴァイオリンに絡んだ後に駆け下り駆け上がるヴァイオリンがオーケストラの盛り上がりを引き出すと、ヴァイオリンはさらに重音を連ねて曲に躍動感をもたらします。再び暗い冒頭の和声、ついで音の厚みと感情の昂りを伴う再現部を経て、最後にヴァイオリンが階段を下っていくようにトリルダウンして静かに終曲。
ラヴェル:チガーヌ
「チガーヌ(ツィガーヌ)」はロマを意味する言葉で、単数形ではロマのヴァイオリン弾きを示すそう。この曲は、ハンガリー出身のヴァイオリニスト、イェリー・ダラーニ(1893-1966)のためにヴァイオリンとピアノ・リュテアル(ピアノに装置をつけてハンガリーの民族楽器ツィンバロンの音を出せるようにしたもの)の編成で1924年に作曲された後、ピアノのパートを管弦楽化したもの。バスク地方出身のラヴェルはスペイン人以上にスペイン的と言われる曲の数々(「スペイン狂詩曲」「ボレロ」など)を作曲してきましたが、この曲では「ツィガーヌ自身以上にツィガーヌ的」と賞賛されたそうです。
曲の構成は、ハンガリーの民族舞踊チャールダーシュの形式に則って緩やかな部分(lassú)と急速な部分(friss)が連なります。最初に独奏ヴァイオリンのエキゾチックなスケールとポルタメント、さらに重音やフラジオレットの多用がもたらす緊迫した演奏が続いた後に、重音トリルの上にシンバルとハープが加わり異世界へ誘われます。警報音のようなフルートをきっかけに曲の雰囲気が変わり、東欧の雰囲気を漂わせる不協和な音のぶつかり→急速な上下行→両手を組み合わせた技巧的なピチカート。その後、休符のたびに指揮者と間合いを測りながら、オーケストラと共に徐々に情熱的な曲調に転じ、最後はアクセルを踏み込んで一気呵成に終曲へ。
これら2曲を通じて、辻彩奈の演奏は一音一音に存在感があり、曲に入り込んでいるのか猫背の姿勢からぐっと踏み込む足や演奏の合間に周囲を睥睨するような身のこなしに、その若さに似合わぬ貫禄のようなものを感じました(一緒に聴いていた相方はそれがちょっと怖くも感じたようでしたが)。なお、アンコールを求める聴衆の拍手に応えて演奏されたのは、ヴァイオリンの音域の広さを極限まで示す無調の短い曲(N響のツイートによれば権代敦彦作曲「Post Festum ~ソロ・ヴァイオリンのための 作品172―第3曲」)でした。
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ
休憩をはさんで演奏されたこの小品が、この日もっとも聴きたかった曲です。「パヴァーヌ」とは16世紀ヨーロッパに起源を持つ宮廷舞踏。題名の意味はラヴェル自身の説明によれば「昔、スペインの宮廷で小さな王女が踊ったようなパヴァーヌ」とのことで、ベラスケスが描いたマルガリータ王女の肖像画をルーヴル美術館で見たことが作曲のきっかけとの説があります。
ラヴェルが学生時代(1899年)に作曲したピアノ作品を1910年に管弦楽化したこの曲は、美しい主題を三度繰り返す間にエピソードを挟む小ロンド形式。「クープランの墓」と同様の小規模編成で演奏され、冒頭の主題は弦楽の低音のピチカートの上でのホルンにより始まり、2度目は木管楽器、3度目はハープの分散和音の上でフルートとヴァイオリン。それぞれ転調しての二つのエピソードの主役はオーボエとフルート。ホルンの暖かい響きにうっとり聞き惚れて、その後も穏やかにたゆたうような曲の進行の中、ノスタルジックなメロディーとラヴェルならではのオーケストレーションの妙を味わいました。幸せ……。
なお、平明なこの曲は作曲当時大衆の人気を博したものの前衛的な気質の芸術家たちに評価されず、ラヴェル自身も工夫がないと卑下していたそうですが、記憶障害を患った晩年にこの曲を聴いて「美しい曲だ。誰が作ったのだろう?」と漏らしたという逸話があるそうです。
ラヴェル:バレエ音楽「マ・メール・ロワ」(全曲)
シャルル・ペローの童話集『マ・メール・ロワの物語』(『マ・メール・ロワ』=「がちょう母さん」。英語の『マザー・グース』はこの本が英訳されてイギリスに受容された後に広く伝承童話・童謡集を示す言葉になったもの)からタイトルを借用したこの曲は、もともと子供のためのピアノ連弾作品として作曲され(1910年)、管弦楽版に編曲された後にバレエ化の依頼を受けて曲を書き足し台本もラヴェル自身が書いたもの(1912年初演)。そのストーリーは「眠りの森の美女」(ペロー)をベースとし、途中に眠っている王女を慰めるための劇中劇「美女と野獣」(ジャンヌ=マリー・ルプランス・ド・ボーモンから)、「一寸法師」(ペロー)、「パゴダの女王レドロネット」(マリー=カトリーヌ・ドーノワから)を挟むというもので、楽曲はこれらの情景を示す曲とそれらの間をつなぐ間奏からなっています。
妖精の園の情景を描く〈前奏曲〉は木管楽器による穏やかな主題から始まり、ファンファーレや小鳥のさえずりと共に、後続する各曲の主題が次々に現れます。引き続く〈第1場:紡ぎ車の踊りと情景〉で紡錘で指を突いたフロリーヌ王女が永遠の眠りにつく場面は弦楽器のピチカート下降とハープのグリッサンド。それまでの王女の動きと共に賑やかだった音楽が悲しげな低音の響きにとって代わられ、フルートとホルンの旋律の中で王女がベッドに横たえられる短い〈第2場:眠りの森の美女のパヴァーヌ〉。ここで紡ぎ車のそばに座っていた老女が衣を脱ぐと実は美しい妖精ベニーニュで、〈間奏曲〉でのその指示により三つのおとぎ話が演じられることになります。
〈第3場:美女と野獣の対話〉では、エリック・サティの「ジムノペディ」を連想させるパターンに乗って軽やかなクラリネットが美女の主題、コントラファゴットの唸るような低音が野獣を示し写実的。2人のワルツがテンポ・音程とも高揚した先に全休止となって美女が野獣の愛を受け入れると、野獣の主題はヴァイオリンに渡されて野獣は王子に変身し、印象的な和音で締めくくられます。〈間奏曲〉を挟んで〈第4場:一寸法師(「おやゆび小僧」とも)〉はきこりに捨てられた7人の子供たちが森を彷徨う場面。不安げなヴァイオリンの動きを背後にオーボエが主題を奏で、道しるべとして落としてきたパンくずもピッコロなどが示す森の小鳥たちに食べられてしまって子供たちはがっくり。続く〈第5場:パゴダの女王レドロネット〉の「パゴダ」とは、ここでは中国の陶製の首振り人形のこと。前置された〈間奏曲〉でハープやチェレスタが中国風の響きを重ね、ついでピッコロの低音域に打楽器も加えた元気の良い五音音階の旋律が人形たちの様子を示します。銅鑼の合図でレドロネットが登場するといったん鎮静化しますが、徐々に盛り上がりを取り戻して最後はシロフォンを中心に小走りの曲調となって終わります。
遠くから鳴り響くホルンの音が王子の訪れを告げ、ヴァイオリンのソロが眠りの森の美女の主題を演奏して〈終曲:妖精の園〉へ。雅やかな弦楽が王女と王子の出会いの場面を描き、次第に楽器の種類と音量とが増して、最後には力強い打楽器群にハープのグリッサンドとチェレスタの輝かしい響きを加えて祝祭感に満ちた主題のリフレインが演奏され、弦楽が余韻を残すかたちで終曲となりました。
この演奏会のチケットをとったのは演奏会当日の2日前。この時期は冬季クライミングシーズン真っ只中なのでチケット発売後もスルーしていたのですが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言のせいで遠出ができなくなったことが怪我の功名で、おかげで前々からいつかはと思っていたラヴェルの音楽に触れる機会を得ることができました。これまでに接したラヴェルの曲の演奏機会は、アリス=紗良・オットによるピアノ独奏(夜のガスパール / 亡き王女のためのパヴァーヌ)、イルミナートフィル(ボレロ)、そしてN響+アリス=紗良・オットの組合せ(ピアノ協奏曲 ト長調)。それぞれに印象深い演奏でしたが、今回のようにまとまったかたちでラヴェルの曲の数々に接したのは初めてす。
そしてもちろん、N響管楽器群の素晴らしい技巧と弦楽のダイナミズムの振幅を自在に操った沼尻マエストロにもブラボー。そのおかげで、管弦楽の魔術師とまで呼ばれたラヴェルの卓越したオーケストレーションを堪能できたことは幸福でした。